「昏睡」
ドイツ語題:Koma(昏睡)
原題:Politi(警察)
2013年

<はじめに>
前作の結末で、ハリー・ホーレは頭と腹に三発の銃弾を受け、死亡したことが暗示されている。この本でも、頭注まではハリーの生死については述べられていない。しかし、ハリーは死んではいなかった・・・
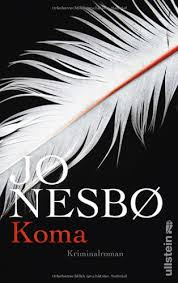
<ストーリー>
ラケル・ファウケの家の戸棚には、拳銃が眠っていた。それは、もともと麻薬組織のボス、ルドルフ・アサイエフのものであった。その拳銃が最後に使用されたのは、オレク・ファウケが、ハリー・ホーレに対して三発の銃弾を発射したとき。ラケルもオレクも、そのピストルが二度と陽の目を見ないことを願っていた。病室では重傷を負ったアサイエフが、昏睡状態で横たわっていた。そして、彼が二度と目を覚まさないことを願っている人物がふたりいた。
警官、エルレンド・ヴェネスラは九月のある夜、オスロ郊外の山道を自転車で登っていた。街のスタジアムからは、サッカーの国際試合の歓声が聞こえてくる。山の上で、彼は自転車を停め、森の中に分け入る。何者かが彼に襲いかかる。
警察学校の実習生シリエ・クラヴセングと一緒に、昏睡中のアサイエフを見張っていた警官、アントン・ミテットは、自分の担当時間の終わる間際、警察本部より殺人事件が発生したため、オスロ郊外の森の中に行くよう指示を受ける。アントンがそこに着くと、既に鑑識のベアテ・レンが来ていた。そこには、顔が識別できないくらい叩きのめされた死体があった。それは、警官、ヴェネスラもので、彼が、数年前全く同じ場所で起こった強姦殺人事件の担当であったこと、そしてその事件は未解決で終ったことが、ベアテの記憶により明らかになる。
オスロ警察で犯罪心理を担当していたストーレ・アウネは、警察を辞め、カウンセリングの診療所を開業していた。家族のために、安定した勤務時間を得るため、警察を辞めたストーレだが、心理カウンセラーとしての仕事に、早くも退屈し始めていた。その日も、彼は金持ちの会社経営者と思われる男の相手を嫌々やっていた。
オスロ警察に、警察官殺人事件の特別捜査本部が設けられ、グナー・ハーゲンがその本部長となる。オスロ警察には、ミカエル・ベルマンという、若い署長が就任したばかりだった。ベルマンは、オスロ市の社会局長である女性、イザベル・スクイエンスと共謀し、麻薬組織のボスであるアサイエフを助け、彼と協力することにより、アサイエフの以外のオスロの他の麻薬組織を撲滅し、その功績で、今の地位を得たのだった。また、ベルマンとスクイエンスは愛人関係にあり、彼等はお互いの配偶者に隠れてホテルで密会をしていた。
警察官殺しの捜査は、進展を見せないまま十一月に入る。スキーリフトの小屋の中で、ひとりの男が殺されているのが発見される。その男も、ベルティル・ニルセンという警察官で、数年前、そのスキーリフト小屋であった、少女の強姦殺人事件を捜査した人物だった。彼は、自分の車でその場所を訪れており、争った跡もない。つまり、二人の警察官は、いずれも自ら捜査したが未解決のまま終わった事件の現場で、殺されていたということになる。
警官のトゥルス・ベルントセンは、大金を受け取り、その金の出所を明らかにできなかったということにより、汚職の疑いで停職処分になっていた。実はその金は、警察の動きを、警察署長のベルマンの命令で、アサイエフに内通することにより、その見返りとして受け取ったものであった。トゥルス・ベルントセンは警察学校時代から、ミカエル・ベルマンの忠実な子分であった。捜査本部長のハーゲンは、ベルマンに、小さな機動力のある組織で捜査を進めることを提案するが、ベルマンはそれを拒否する。逆に、ベルマンはアサイエフに対する監視はもう必要ないので止めることをハーゲンに提案する。ハーゲンは、ベアテ・レン、カタリーナ・ブラット、ビヨン・ホルム等、かつてのハリーのチームメンバーを集め、ベルマンには内緒で、少人数の捜査班を結成する。
特別捜査班の一員、カトリーネ・ブラットは、殺された二人の警官が捜査していた少女の強姦殺人事件に、共通の容疑者として現れたヴァレンティン・ギェルトセンのことを思い出す。彼は、両方の件とも、アリバイが成立し、起訴されることはなかった。その両方のアリバイとも、彼のアパートに住んでいた、イリア・ヤコブソンという女性の証言によるものだった。ブラットは、イリアを訪れる。そして、彼女が嘘の証言をしていたことを知る。
ヴァレンティンはその後、別の事件で服役していた。しかし、隣の房の男の脱獄事件の際、ヴァレンティンは刑務所で死亡していることになっていた。カトリーネ・ブラットは、死亡していたのはヴァレンティンと同じ刺青を施された隣の房の男で、脱獄していたのはヴァレンティンであることを突き止める。リコという男が、ヴァレンティンが殺した隣の房の男に同じ刺青をしたと証言する、他人の死体はその刺青によってヴァレンティンのものであると判定されたのだった。病院のアサイエフは意識を取り戻す。しかし、その直後、心臓麻痺で死亡する。
カトリーネ・ブラットは、警察学校を訪れる。警察を辞めたハリー・ホーレは、現在、警察学校の講師として働いていた。ハリーが、銃弾を浴び重傷を負いながら、どのようにして命を取り留めたのか、彼を銃撃したのは誰なのかは、警察にとって謎のままだった。講義の後、カトリーネはハリーが同僚のアーノルド・フォルケスタッドと一緒に使っているオフィスを訪れる。カトリーネはハリーに、捜査を手伝ってくれるように頼むが、彼は拒否する。
ベアテ・レンもハリーにハリーの負傷した事件の説明と、警官殺し事件の捜査班への参加を求める。ハリーは再び拒否するが、ベアテに、殺された二人の警官が銃を持たないで現場に行ったことに注目するように言う。つまり、ふたりとも、おそらく見知らぬ人物ではなく、同僚に呼び出されたものだと。
ハリーが深夜警察学校の事務室で働いていると、警察学校の女子学生シリエが入ってくる。彼女は自分を抱くようにハリーを挑発する。挑発に乗らないハリーを彼女は翌日強姦されたと訴えるが、ハリーと、同僚のアーノルド・フォルケスタッドの機転によって、それがシリエの芝居であることが分かる。
ベアテ・レンは市電に乗り込むヴァレンティンを発見する。彼女は、その市電を包囲させるが、ヴァレンティンは既に逃げた後だった。ストーレには、カウンセリングに訪れていた男が、その刺青からヴァレンティンであることが分かる。
ハリーはラケレと結婚することを決意。ベアテ・レンに結婚の証人になってくれるように依頼に行く。ハリーがベアテ・レンを訪れると、彼女は殺され、バラバラにされゴミ箱に入れられたその死体は、まさに収集車によって運び去られるときであった。ベアテ・レンの葬儀の席で、ラケレは、ハリーに警察の捜査班に戻ることを懇願する。ハリーは、ようやく重い腰を上げ、外部のアドバイザーとして、ストーレ・アウネと共に捜査に参加することになる。
<感想など>
「ハリー・ホーレ」シリーズの第十作、二〇一四年現在の最新作である。二年前に発表された「Gjenferd」(ドイツ語題Die Larve 幼虫)から話が続いている。私は前作を読まずに、いきなりこの本を読んで、少し唐突な気がした。やはり、シリーズ物はきちんと書かれた順番に読んだ方が良いということだ。
前作の最後で、ハリーは三発の銃弾を浴びているという。そして、そこでは彼の死が暗示されているという。しかし、ハリーは生きていた。警察学校の教官をやっている。
「主人公は殺されない」という、推理小説の不文律に挑んでいるのがヨー・ネスベーだと思う。シリーズの最初の本を読んだ時、重要人物、副主人公ともいえる女性が、あさりと殺された。周囲の人物が何人殺されようとも、主人公は間一髪のところで命を取り留めるというのが、シリーズものの推理小説のパターンである。一応、前作の終りで三発の銃弾を浴び、ハリーは死ぬことが暗示されている。しかし、さすがにヨー・ネスベーもハリーなしでは、続編が書けなかったと見えて、彼が奇跡的に助かったことにし、彼を警察学校の教官として復活させている。読者は、カトリーネ・ブラットが警察学校を訪れるまで、ハリーが生きているのか、死んでいるのか知らないままに読み進まねばならない。さすがに、ハリーの命を助けた「ご都合主義」の埋め合わせをしなければならないと考えたのか、ヨー・ネスベーはハリーの最良の同僚であり理解者のベアテ・レンを警察官連続殺人事件の被害者として無残な形で殺している。
警察官の連続殺人事件。次々と容疑者が浮き上がっては消える。少女強姦の罪で服役しながら脱獄したヴァレンティン・ギェルトセン、警察署長のミカエル・ベルマンとその協力者であるトゥルス・ベルントセン、ハリーに対して異常な執着を見せるシリエ・クラヴセング、犯人は彼らのひとりなのか、それとも他に居るのだろうか。
ヘニング・マンケル、スティーグ・ラーソンが、ミリオンセラーとなり、北欧の推理小説が世界を席巻したが、このヨー・ネスベーが、全世界での販売部数では、前述の二人を抜きつつあるという。一見、粗っぽい書き方のようだが、前に出た小さな一見何気ないエピソードが、後で実に大切な役割を演じるように、実は緻密に構成されている。
例えば、カトリーネがハリーに警察に戻るように勧めたとき、ハリーは警察官として働いている時は、自分の恋人の息子のオレクの誕生日さえしばしば忘れてしまうような忙しい毎日であったと振り返る。家に帰って、初めてオレクの誕生日であることを思い出し、煙草を買ってくるという理由でもう一度車で出る。近くのガソリンスタンドでCDなどを買い、それを玄関でハグをする際にオレクに見つからないようこっそりとラケルに渡す。ラケルはそれを包装し、前から買ってあったように「ハリーから」と言ってオレクに渡す。ハリーが警察官として以下に忙しく、家庭を顧みなかったかというエピソードかと思うが、これが最後に実に重要な役割を果たすことになるのである。
「荒っぽいようで、実に芸が細かい」、これは物語の構成に対しても、ハリーの性格に対しても言えるものである。ハリーはあくまでも「はみ出し警官」であり、今回も、警察の規則からも、法律からも、社会通念からも、大きく離れた行動を取る。犯人の意外性にこだわる余り、犯人以外の容疑者を細かく書き込み、ボリュームが増えている。長かったが、それなりに退屈せずに読めた。
(2015年1月)