�u�A���v
Die Heimkehr
2006�N
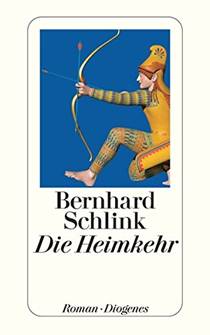
���X�g�[���[��
�@�q���̍��A�u���v�A�y�[�^�[�E�f�o�E�A�[�̓h�C�c�̂��钬�ŕ�e�Ƃӂ���ŕ�炵�Ă����B�������A�ċx�݂ɂȂ�ƁA�X�C�X�̌̔ȂɏZ�ށA�����̑c����̉Ƃʼn߂������ƂɂȂ��Ă����B�u���v�͉Ă̏��߂ɁA�����Ă��͓S���ŁA���̐ؕ������̂Ȃ��Ƃ��̓g���b�N�ɏ悹���āA�c����̏Z�ރX�C�X�̒����������B���e�͖S���Ȃ����ƕ�������Ă����B�u���v�͎����������X�C�X�l�ł��邱�Ƃ��C�ɓ����Ă����B
�@�c����̉Ƃł́A�������ۂ̌J��Ԃ��ƁA�Î₪�x�z���Ă����B�c���͈�x�č��ɓn�������A���[���b�p�ɖ߂�A�e����]�X�Ƃ�����A�̋��̃X�C�X�ɖ߂����Ƃ����B�u���v���K���悤�ɂȂ��������A�c����͒ʑ������G���̕ҏW�����āA���v�𗧂ĂĂ����B�c����͎��������̑��q�A�u���v�̕��e�ɂ��āA�]�葽�������Ȃ������B���e�͖@�����w�сA���ƕ��w���D�B�����Đԏ\���Ƃ��đ���E���ɏ]�R���A���̎������Ƃ������Ƃł������B
�@�G���̕ҏW�����Ă���W�ŁA���e��Q�����肪�c����̉Ƃɂ͑�R�������B�܂������M�d�ł������\�N��A�u���v�́A���̌��e��Q��������ƂɎ����A��A���ʂ��m�[�g����Ɏg���Ă����B�c����́A�u���v�ɗ��Ɂi�܂�{���͕\�j�ɏ����Ă���A�����̌��e��ǂނ��Ƃ��ւ��Ă����B�u���v�������Ԃ���𒉎��Ɏ���Ă����B�������A������A�u���v�͂��̌��e��ǂ�ł��܂��B����̓��V�A�̕ߗ����e������E�����A���̖��Ɍ̋��ɖ߂����h�C�c���A�J�[���̕���ł������B�������A�����̏�����Ă���Ō�̃y�[�W�A�܂�u���v�ɂƂ��Ă̓������̍ŏ��̃y�[�W�́A���Ƀ��������Ƃ��Ďg���A�̂Ă��Ă����B���āA�u���v�͂��̌�����m�肽�������߂ɁA�c����̖{�I�ɂ���G���̃o�b�N�i���o�[��T�����B�������A���̕���̈�����ꂽ���́A���̂��ǂ��ɂ�������Ȃ������B
�@�u���v�͑�w�ɐi�݁A�ċx�݂ɑc����̉Ƃ�K��邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�B�����āA�A�����镺�m�̕���̂��Ƃ��A�������L���̕Ћ��ɒǂ�����Ă��܂����B����N�̃N���X�}�X�A�u���v�͋v���Ԃ�ɑc����̉Ƃ�K���B���낻�뎀�̋߂����Ƃ�������c����́A�g�Ӑ�����i�߂Ă���A�u���v�͊��₻�̑��̕���c���ꂩ������p�����ƂɂȂ�B�����āA�u���v���c����������̂́A���ꂪ�Ō�ɂȂ����B���̒���ɑc����͌�ʎ��̂ŖS���Ȃ�������ł���B
�@��w�𑲋Ƃ����u���v�́A���m���̎擾��ڎw���B����A���F�B�Ɠ������n�߁A�q�����ł���B�������A���鎞�A�u���t�v�Ɉˑ������d������̑S�Ă����ɂȂ�A��l�ŕč��ւƗ����B�T���t�����V�X�R�ŁA�u���v�́u���t�v�ɗ���̂ł͂Ȃ��A��蒼�ړI�Ȑl�ԂƐl�Ԃ̃R���^�N�g�����߂āA�}�b�T�[�W���w�ԁB�����āA�}�b�T�[�W�t�̎��i�����B�������A�u���v�͂ǂ����Ă�������č��Ɠ����ł��Ȃ��B�����āA�Ăуh�C�c�֖߂邱�ƂɂȂ����B
�@�h�C�c�ŁA�u���v�͂���o�ŎЂɏA�E���A�@���W�̏o�ŕ���S������B�A�p�[�g����āA���܂ꂽ���ׂ̗̒��ɏZ�ނ��ƂɂȂ�B�u���v�́A���z���ו��̔��̒�����A�q���̍��ɓǂA�u����h�C�c���̋A���̕���v������B�u���v�͂��̕���Ɉ������A�ǂ݂ӂ���B
�@���̏����̎�l���́A�J�[���Ƃ����j�B�ނ́A���l�̒��Ԃƈꏏ�ɁA�V�x���A�ɂ��郍�V�A�̕ߗ����e����E������B�����āA�������������āA�V�x���A�����f����B�ނ́A���̓r���A�͐s���|���B�������A�J�����J�Ƃ��������ɏ�����A�������ޏ��ƈꏏ�ɉ߂����A�̗͂�����B�J�����J�Ɉ���Ɖ��`��������J�[���ł��邪�A�]���̔O�ɂ͏��Ă��A�ޏ��̌�������A�Ăуh�C�c�̌̋���ڎw���B�����āA���X�̋��̖��ɂ��ǂ�����̋��̒��A�ނ͎����̍Ȃ̉Ƃ̃h�A�̑O�ɗ����A�x���������B������͍Ȃ��o�Ă����B�������A���̘r�ɂ͐Ԃ�V��������Ă���A���̌��ɂ͐V�����v�Ǝv����j�������Ă����E�E�E
�@�u���v�́A�J�[���̋A���̕���ƁA�Ñ�M���V�A�̃z�[�}�[�̏������u�I�f���b�Z�C�A�v�̗ގ��_�ɋC�Â��B��҂́A�Ñ�M���V�A���w�ɑ��w�̐[���l���ł���ɈႢ�Ȃ��ƁA�u���v�͗\������B
�@�u���v�J�[���̋A���̏�ʂɕ`����Ă���X�̗l�q���A�������Z�ނ��ƂɂȂ������ƍ������Ă��邱�ƂɋC�Â��B�����āA�u���v�́A����̕���ɂȂ����Ǝv����Ƃ�˂��~�߂�B�D��S�ƒT���S�ɂ���ꂽ�u���v�́A���̉Ƃ̌��ւ̌Ăї��炷�B�����ɂ́A�ЂƂ�̏������Z��ł����B���̉Ƃ͂����Ɣޏ��̕�e���Z��ł������A�����ŋߖS���Ȃ��Ă����B�P�j�A����ŋߋA���ė����ޏ��́A�S���Ȃ�����e�ɑ���A�����ɏZ�ނ悤�ɂȂ����Ƃ��������Ƃł������B
�@���̉Ƃ̏Z�l�o�[�o���Ɂu���v�͍D�ӂ����B�����āA�T����ޏ��ƈꏏ�ɉ߂����悤�ɂȂ�B�������A�o�[�o���́u���v�ɁA�����ɂ̓P�j�A�ɂ��鎞�Ɍ����������肪���邱�Ƃ���������B���̒j�̓W���[�i���X�g�ŁA���݃X�[�_���Ɏ�ނɍs���Ă���Ƃ����B
�u���v�ƃo�[�o���́A�ޏ��̉Ƃœ������n�߂�B�������ޏ��̕v�A�A�����J�l�̃W���[�i���X�g���ˑR�A���Ă���B�u���v�͕��������ӂ�������ڂɌ��Ȃ���A�ق��ĉƂ��o��B
�@�����̎�l���A�J�[�����A�����āA�����̍Ȃ�K�ꂽ�Ƃ��ɖ���������]���A�������g��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���Ƃ�������ł��낤�B���̌�A�o�[�o���́u���v�ɑ��āA���鎞�͌��ւ̃h�A��@���A�܂����鎞�莆�ŁA�R���^�N�g�����݂�B�������A�u���v�͂�������₵������B�������A�u���v�́A�ޏ��Ɖ߂��������̒������邱�Ƃ������A�����ɏZ�ݑ�����B�����āA�U��ꂽ�����̐g�̏���A���s�I�ɗF�B�ɘb���������āA�������Ԃ߂�B
�@�o�[�o���ƕʂꂽ�u���v�͐V�����������n�߂�B�o�ŎЂł́A�V������悪�҂��Ă����B�d���̍��Ԃ�A�x�b�h�̒��Łu���v�́u�I�f���b�Z�C�A�v��ǂ݂ӂ���B�����āA�����Ǝ�l���̋������ׁA��l���̒H��������Ǒ̌����Ă݂悤�Ƃ���B
�@�����ꂽ�ŏ��̍Ȃ̃��F���j�J���A�\�ɂȂ鑧�q�̃}�b�N�X���u���v�ɑ����āA�V�����{�[�t�����h�Ɨ��ɏo��B���̊ԁA�u���v�̓}�b�N�X�ƁA�j���m�́A��ȁA�������y���������𑗂�B�������A�u���v�͈��������A���m�̋A���̕���̍�҂��N�ł��邩��T�邱�Ƃ͂�߂Ȃ������B�����āA�ːЋǂ̎�������A���O�Z�N�ォ��l�\�N��ɁA���݂̃o�[�o���̏Z��ł���ƂɁA�ЂƂ�̊w�������h�����Ă������ƁA���̊w������ɑ�Ƃ̃r���f�B���K�[�v�l�̖��A�܂�o�[�o���̕�ɋ������Ă������Ƃ�m��B�u���v�͂��̊w���������A����̍�҂ł���ƒ�������B
�@�u���v�̓o�[�o���̖��A�}���K���[�e��K���B�����āA�o�[�o���ƃ}���K���[�e�̕ꂪ�c�����莆��ǂށB���̒��ɁA���h�����Ă����w������̂��̂����ʂ������B�w���̓t�H���J�[�E�t�H�������f���Ƃ������O�ŁA��N�A�����̃i�`�X�̐�`�G���ɁA��ӂ����g������悤�ȕ��͂������Ă����B�����āA�ނ́A�q�g���[�̉E�r�ł������J�[���E�n���P�Ƃ����l���ɐM�p����Ă����Ƃ������Ƃł������B�u���v�̓}���K���[�e���A�{���̓t�H�������f���̖��ł͂Ȃ����Ƌ^�������B�u���v�̓t�H�������f�����o�[�o���ƃ}���K���[�e�̕�ɑ������莆��A�ނ̏������G���̐ؔ������R�s�[����B
�@�t�H�������f���̋L���̒��ŁA���j���O���[�h�U�h��́A�u�I�f���b�Z�C�A�v�ƕ��ԃz�����X�̏������A�u�C���A�X�v�ɕ`���ꂽ�g���C�푈�Ɣ�r����Ă����B�ނ́A�M���V�A�ÓT�ɐ��ʂ��Ă����̂ł���B�u���v�́A���m�̋A������́u�I�f���b�Z�C�A�v�Ƃ̋��ʓ_����݂Ă��A�����̍�҂̓M���V�A�ÓT�ɐ��ʂ��Ă���l���A�܂�t�H�������f���ł��邱�Ƃ��m�M����B�t�H�������f���̂��̏����ł��邪�A�`�F�R�ŏ�i�̃n���P�ƂƂ��Ƀp���`�U���ɕ߂��ꂽ���A���̌�E���ɐ������Ă����A���̒E���̌����A���m�̋A������̃l�^�ł��邱�Ƃ͗e�Ղɑz���ł����B�u���v�̓t�H�������f���Ɋւ���X�Ȃ���邽�߂ɁA�V���L�����ڂ���B�������A����ɂ͑S�������͂Ȃ������B
�@��e�̒�N�̋L�O�ɁA���͕�e�Ə����s�ɏo��B�r���A�c����̏Z��ł����X�C�X�̒���K���B�����ŕ�e�́A���߂ĕv�Ƃ̏o��ɂ��Č��B��e�͂��̂Ƃ��u���X���E�ɏZ��ł����B�v�lj����������\�A�R�ɕ�́A�U������A�ח�����l���e�͌��Ă����B�n���P�����̃u���X���E�h�q�̎i�ߊ��ł������B���l�l�N�ɕ�̓X�C�X�l�́u���v�̕��e�Ƃ����Œm�荇�����ɗ�����B��e�͔D�P������B���͒����ח����鐡�O�ɁA��e��������E�o�ł���悤�ɂƁA�X�C�X�̃p�X�|�[�g��n���B�������A���̌�A��e�̖ڂ̑O�ŁA���͏e�e�ɓ|�ꂽ�Ƃ������Ƃł������B
�@���j�͋}�W�J��������B�x�������̕ǂ̕������Ƃ����u���v�́A���̗��j�I�ȓ��ɁA���j�I�ȏꏊ�ւƌ������B�u���v�́A���x�������̒������܂悢�����B�����āA�����Ɏ����̎q���̍��̕��i������B�����ԓ��x�������؍݂����u���v�́A�Ō�̓��ɁA��w�̖@�w����K���B�Ђ��Ȃ��Ƃ���A���̊w���̋��������ƒm�荇���ɂȂ����u���v�́A���h�C�c�̖@���ɂ��Ă̍u�`�N�Ԉ����邱�ƂɂȂ�B�o�ŎЂւ̋Ζ��𑱂��Ȃ���A�u���v�͏T�Ɉ�x��s�@�Łu���v�ɔ�сA��w�ōu�`������B���肵���A��������̋@�^�����܂�A�u���v�̍u�`�͊w�������̐l�C���W�߂�B
�@�u���v�́A���x�������ɏZ�ނЂƂ�̘V�w�l����̎莆�����B�ޏ��́A�u���v���t�H���J�[�E�t�H�������f���̏�����T���Ă���Ƃ����V���L�������āA�ւ���悱�����̂ł���B�V�w�l�́A�t�H�������f�����A���A�E�B�[���o�g�̃��_���l���@���^�[�E�V�����[�Ƃ̖����A���{�@�ւ̐V���̕ҏW�����Ă������ƁA�����āA�ނ��˔@�Ƃ��Ďp�����������Ƃ��u���v�ɘb���ĕ�������B
�@����T���A�x����������̋A��̔�s�@�ɁA�u���v�̓o�[�o���Ə�荇�킹��B���̍��A�u���v�̊w�Z�ƒ�g�������o�[�o���̊w�Z�́A�����̌𗬂����Ă����̂ł������B��s�@���~�肽���̓o�[�o���ɁA�u���v�͂���߂��Ă����悤�ɗ��ށB�ŏ��͔��������o�[�o�����A�Ăсu���v������A�ӂ���͉��߂ĕt�������n�߁A�Ăшꏏ�ɕ�炵�n�߂�B�o�[�o���Ƃ̌�����^���ɍl���o�����u���v�́A�ːЋǂ�K���B�����āA�����Ŏ����̕ꂪ�����ɂ͌������Ă��炸�A�����̐����̐��͕����́u�f�o�E�A�[�v�ł͂Ȃ�����́u�O���t�v�ł��邱�Ƃ�m��B�u���v�͕�e��K�ː^���ɂ��ċl�₷��B��e�͕s���s���ɁA�������u���v�̕��Ɛ����Ɍ������Ă��Ȃ��������Ƃ�F�߂�B�u���v�͎��������e�̐��𖼏�鎑�i�̂Ȃ����Ƃ�m��A�����ƕ��e��c����Ƃ̂Ȃ��肪�����Ȃ����悤�Ɋ�����B
�@�u���v�́A�o�[�o���Ƃ̌����������n�߂�B�������A���̈���ŁA���̌̋��ɏZ�ޓ�������K�ˁA���Ɋւ�������W��ȂǁA�����̒a��������^���̋����𑱂���B�u���v�͂�����A���͏o�ŎЂɑ����Ă����A�����J�̖{�Ɋ�𗯂߂�B��҂̓j���[���[�N�ɂ���^��w�̖@�w�������u�W�����E�f�E�o�E�A�[�v�A�薼�́u�@���̃I�f���b�Z�C�A�v�B���e�̖��O�ł���u���n���v���A�����J���ɔ�������u�W�����v�ƂȂ�B���e�͖@�����w��ł����B�����āA�u�I�f���b�Z�C�A�v�B�u���v�́A���̍�ҁA�f�E�o�E�A�[���A�����̕��e�ł���ƂƂ��ɁA�{�����߂Ă��������̍�҂ł����邱�Ƃ�����B��e�͈�т��āA���͎��Ɓu���v�Ɍ��������Ă����B�u���v��e���A����܂Ŏ����ɑ��Đ^�����B���Ă������Ƃɜ��R�Ƃ���B
�@�u���v�͕�e�ɐ^�������悤�ɔ���B�����āA��e�͂��ɐ^�������B���n���E�f�o�E�A�[�̓u���X���E�ł͎��̂ł͂Ȃ������B�ӂ���͂����ŕʂꂽ���A���e�͐푈�̏I�������̈��l�Z�N�A��e��K�˂Ă����B�����āA���炭�̊ԁA��e�̂��Ƃɑ؍݂��A���܂ꂽ����́u���v�𐢘b������A�A�����J�Ɍ����Ĕ����Ă������B���l�̌�������Ƃ��A���n���͕�e�ɂЂƂ̏������Ă���B�ނ̕���ɑ��Ă������������Ƃɂ��Ă����Ăق����ƁB���n���͐푈���̍s���ɂ��A���x�@�ɒǂ��Ă���A���ꂩ�瓦��邽�߂ɂ́A���Ƃ������Ƃɂ��āA���̃A�C�f���e�B�e�B�[����ɂ��邵�����@���Ȃ������̂ł���B��e�͂�������m���A���̌�A���n���Ƃ̖��A�u���v�ɑ��Ă��A�ނ̕���ɑ��Ă�����Ă����킯�ł���B��e�̂��Ƃɑ؍݂��Ă����������̊ԂɁA���n���͏����ł����l�̌�X�̐����̗ƂɂȂ�悤�ɂƁA�������������B���ꂪ�u���m�̋A���̕���v�ł������B
�u���v�́A���ƍĉ�邽�߁A�o�[�o�����c���ăj���[���[�N�ւƌ��������S������B
�@�j���[���[�N�ɒ������u���v�́A�f�E�o�E�A�[�����̋����Ă����w�������A�U���Ŕނ̍u�`�ɒ��u���Ƃ��ĎQ������B�f�E�o�E�A�[�̍u�`�͊w���ɐl�C���������B��e�Ǝ������̂Ă����e�ɔ����������Ȃ�����A�@���ƂƂ��āA�ނ̍u�`�̓��e�ɂ͋��Q���ւ����Ȃ��B������A�u���v�̓f�E�o�E�A�[�̉Ƃ̌��ւŁA�Ⴂ�����Ƃӂ���̎q��������B���ꂪ�ނ̍ȂƎq���ł���ɂ������Ȃ������B�u���v�́A�����̎�l���J�[�����A�����̌̋��ɂ��ǂ蒅������A�Ȃ̉Ƃ̑O�Ŏ��Ռ����A�����ł��̌�����B
�f�E�o�E�A�[�́u���v���C�ɓ����Ă���悤�ł������B�u���v�͔ނ̉Ƃɏ��҂���A���ɂ́A�ނ̎��I�ȃ[�~�i�[���ɏ��҂���邱�ƂɂȂ�B���̎Q�������[�~�i�[���ŁA�u���v�͕��e�ł���A��w�����ł���A�{�����߂Ă��������̍�҂ł���W�����E�f�E�o�E�A�[���邢�̓��n���E�f�o�E�A�[�̐^�̈Ӑ}��m�邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�����z�Ȃǁ�
�@����͎l�l�̒j�̋A���̕���ł���B
�@�u���v
�A�@���e�A
�B�@�����̎�l���ł���J�[���A
�C �I�f���b�Z�E�X�B
���ꂼ�ꂪ�A�̋�����������A�̋����A�̋��ւ̓���H��B�������A�u�̋��v�͒P�ɕ����I�ɁA���܂ꂽ�ꏊ���w�������ł͂Ȃ��B�����̃��[�c��T�����߁A�����ɖ߂��Ă����Ƃ������Ƃ����Ӗ�����B�@
�@�u���X���E�̊ח��͂��Ƃ��A�x�������̕ǂ̕��瓌���h�C�c�̓���A���̌�u���v���u���v�Ɉ��ݍ��܂�Ă����ߒ��ȂǁA�h�C�c�̗��j����M����ׂ��������U��߂��Ă���B���̉ߒ������ۂɑ̌��������ɂ͉����������Ƃ��肾���A�̌����Ȃ��������ɂ͕��ɂȂ�Ǝv���B
�܂��A�u�I�f���b�Z�C�A�v�̃G�s�\�[�h���ӂ�Ɏ������Ă��āA���̖{��ǂނ����ŁA���ƂȂ��u�I�f���b�Z�C�A�v�������悤�ȋC���ɂȂ�B���ꂾ���ł��A���Ȃ�̉��l�͂���B�\���I�ɂ́A�ŏ��ɃM���V�A�ÓT�́u�I�f���b�Z�C�A�v������A��������~���ɁA�����m��ʍ�҂ɂ��u�h�C�c���J�[���̋A������v���������B���̍�҂ƌ��m��ʎ����̕���T���Ɂu���v�������B�����āA���e�����̍�҂ł���A���e���u�I�f���b�Z�C�A�v�Ɠ����悤�ȕ��Q�����Ă��邱�Ƃ�m��B���Ȃ蕡�G�ȗ��ݍ����ł���B�u���v���u�I�f���b�Z�C�A�v��ǂ݂Ȃ���A�ߏ��̐l�����A�X�[�p�[�̃��W�W��A���������c�̃����o�[�Ȃǂ��A���̓o��l���ɓ��Ă͂߂Ă������͂Ȃ��Ȃ��ʔ����B
�S�҂�ʂ��āA�ЂƂ̏͂������Ă��܃y�[�W�B�Z���G�s�\�[�h���A�˂��Ă���̂ŁA�y���ɓǂ߂�͗ǂ��B
�@�f�E�o�E�A�[�����̏�����Ɠ��̎�e�_�A�u�P���͕��ՓI�Ȃ��̂͂Ȃ��A�����܂Ŏ��l�ɂ��B���ꂪ�؋��ɁA���鎞��ɂ́w�P�x�Ƃ��ꂽ���Ƃ��A�ʂ̎���ɂ́w���x�ɂȂ邱�Ƃ�����ł͂Ȃ����v�Ƃ����̂��ʔ��������B�f�E�o�E�A�[�����́A�����̐����w���ɕ����点�邽�߂ɁA�Ō�ɂ͐�����|����Ȏ��������݂�B���ꂪ�ނ́u�����v�ł���ƕ�����܂ł́A���Ȃ�n���n���E�h�L�h�L�������A���ꂪ�㔼�̎R��ƂȂ�B
�������A�V�������N�̕���̎�l���͂ǂ����Ă������ތ^�I�Ȃ̂ł��낤���B�u�N�ǎҁv���u�S���f�B�E�X�̗ցv���A��l���́A�@����������A�l�t�������̉���ȁA�ǂ��������i�ƍs���o�^�[�����������O�\��̒j���B���́i�܂�M�҂́j�A���́u�A���v��{�œǂ݂Ȃ���A�Ԃ̒��ł̓I�[�f�B�I�b�c�œ������V�������N�́u�S���f�B�E�X�̗ցv���Ă����B����ƁA�b�Ɠo��l�����]��ɂ����ʂ��Ă���̂ŁA���̒��ŁA�X�g�[���[���������Ă��܂��č������B���́A�V�������N�́A�����ƈ�����^�C�v�̐l�Ԃ�`���Ȃ��̂ł��낤���B�ނɂ͂��ꂾ���̗͗ʂ͂���Ǝv���̂����B
�܂��A�X�g�[���[�̓W�J�̒��ŁA�ЂƂ�����Ȃ��_������B���́A�u���v�́A�u�@�w�̃I�f���b�Z�C�A�v�̕M�ҁA�W�����E�f�E�o�E�A�[�Ȃ�l�����A�����̕������ł͂Ȃ��A�u���m�̋A�҂̕���v�̍�҂ł���ƕ��������̂��B���ꂪ������Ȃ��B
�u�Ӗ��[�v�Ȑl�����������o�ꂷ��B�����̐l�����A����̒��ŏd�v�Ȗ������ʂ����̂��Ǝv���ƁA��x�o�ꂵ�������ŁA���ǂ��̌㉹�������Ȃ��Ƃ��������q��������B�Ⴆ�A�u���v�̏��N����A�c����̉Ƃ̗Ƃɂ������`�A�Ƃ��������B�u���v�X�J�[�g���グ�ĉA���������ėU���B���ꂾ���B���̑��A�u���v�̋߂�o�ŎЂɃA���o�C�g�ɗ��Ă����x�b�e�B�[�i�B�u���v�Ƃ̊W����킹�Ȃ���A���������B�u���������o��l���v�������������ƁA���̂��߂ɂ��ꂾ���̐l����o�ꂳ���Ȃ�������Ȃ��̂��ƁA���̈Ӗ��ƌ��ʂɂ��čl���Ă��܂��B
���������āA������ƐF�X�Ȃ��Ƃ��l�ߍ��݂����B�]��ɂ��b���L���肷���āA���A���G�ɓ���g�݂����āA�˘f���Ƃ��낪�������B
�@�����̃v���b�g�����݂��ɓƗ����Ȃ�����A�I�݂ɗ��ݍ����A���˂��Ă����l�́A�G�~���[�E�u�����e�́u�����u�v���v���o������B�����ɓǂݏI��������̐[����J�����u�����u�v�̂���Ɏ��Ă���B�u�J�[���̕���v�́A�푈���ɃE�N���C�i�œ|�ꂽ���m�ƁA�����T���Ȃ̕���A�\�t�B�A�E���[�����ƃ}���`�F���E�}�X�g�������j�剉�̉f��u�Ђ܂��v���v���o�������B�Ō�̃f�E�o�E�A�[�����̊��́A�܂��ɉp����[���b�p�ň�Ă��r�����A���A���e�B�[�E�V���[�u�r�b�O�E�u���U�[�v��f�i�Ƃ�����B���̈�ۂ����������悤�ɁA���̏����A������Ɛ����R�߂���Ƃ����̂��M�҂ł��鎄�̌��_�B
�i2007�N1���j�@