ドナ・レオン
コミッサリオ・ブルネッティ・シリーズ
シリーズではブルネッティの戦う相手が変わる。芸術家、弁護士、実業家、美術品の偏愛者などがこれまでの相手であった。今回は、「貴族」である。この物語の中でも書かれているが、現在のイタリアには貴族は存在しない。現在は単に「名門」と呼ぶべきなのかも知れない。しかし、代々、「伯爵」などの称号を受け継いできた家系の長に対して、今もヴェニスの人々はその称号を持って呼んでいる。しかし、イタリアの「貴族」は、過去の遺産を食い潰すのではない。その影響力を最大に生かしてビジネスに励み、新たな「経済的な特権階級」としての道を歩んでいる。
第七話。
原題:A Noble Radiance 「高貴な輝き」
ドイツ語訳:Nobiltá「高貴な人」
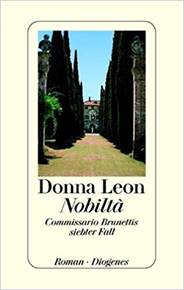
ドロミテの山麓、長年誰も住む者のいない家をあるドイツ人が買った。その敷地内の草を刈っている人間が、白骨化した若い男の死体を見つける。死体の頭蓋骨には弾丸の貫通した痕があり、傍にはヴェニスの名門ロレンツォーニ家の紋章の入った指輪が転がっていた。ロレンツォーニ家では、二年前、跡取りの一人息子、ロベルトが誘拐されていた。彼は父親の別荘の門前で何者かに拉致された。犯人からは、二度身代金要求の電話があった。父親はテレビに出演し、涙ながらに犯人に息子を返すように訴える。しかし、その甲斐もなく、その後、犯人からの連絡も、ロベルトの消息も途絶えたままであった。
ドロミテの警察から連絡を受け、死体の身元確認を依頼されたブルネッティは、死体の歯型と歯医者に残る記録から、白骨死体が誘拐され行方不明のロベルトであることを確認する。彼はその知らせを届けるためにロレンツォーニ邸を訪問する。そこで、コンテ・ロレンツォーニ(ロレンツォーニ伯爵)、ロレンツォーニ夫人、養子のマウリツィオにロベルトの死を告げる。伯爵は名門の家系の誇りを極めて重んじる人物、夫人は誘拐事件以来生ける屍と化し、マウリツィオは妙に野心的な若者である。誘拐事件から殺人事件へと切り替えられた二年前の出来事の捜査を、ブルネッティは再開する。
ロベルトを知る人々を訪ね話を聞くうちに、ブルネッティはロベルトが学生の頃から、無気力かつ無能な人間で、大学卒業後、何とか父親の経営する運送会社に籍を得たものの、接待と荷物の運び屋以外に仕事らしい仕事をしていなかったことを知る。それに対して、養子のマウリツィオは有能で、商才に長けた男であった。ただ、マウリツィオは癇癪持ちで、頭に血が上ると前後の見境いがなくなる性格の男でもあった。無能な実子、有能な養子、父親の三者間の葛藤が、この事件の重要な鍵を握るとブルネッティは推理をする。また、ロベルトの誘拐の現場を訪ねたブルネッティは、ロベルトが車から降りるきっかけとなった自動扉の不作動が、内部から仕掛けられていた事実にも注目する。
ロベルトが誘拐される直前に、東ヨーロッパから帰った彼が体調を崩していたことをブルネッティは知る。そして、検査結果を医師から取り寄せる。その結果により、ロベルトが当時、致死量の放射線を被曝していたことを知るのである。彼は、誘拐直前のロベルトの行動、彼の被爆、父親のビジネスから、ひとつの仮説に辿り着き、それをコンテ・ロレンツォーニに問い質そうとする。
そのとき、同僚のヴィアネリがロレンツォーニ家の第二の惨劇の知らせをもたらす。
今回、ブルネッティは捜査を始めるにあたり、これまであまり関係がしっくりといっていない義父に電話をする。彼の妻、パオラはやはり「貴族」あるいは「名門」の一人娘である。義父も「コンテ」、「伯爵」と呼ばれており、ロレンツォーニと同じく事業にも成功し、ヴェニスでも有数の金持ちなのである。「蛇の道は蛇」と言うと適当でないかも知れないが、「名門」の家庭について調査するには、やはり「名門」の人間のアドバイスを仰ぐというのが一番と言うわけであろう。
久しぶりに、義父と食事を共にすることになったブルネッティは、義父から意外な指摘を受ける。それは、妻のパオラが、家庭で不幸せだというのである。パオラが父親にそう言ったわけではない。あくまで父親の想像なのであるが。その原因は、ブルネッティがあまりにも仕事に打ち込みすぎるからだと言う。そのときブルネッティは、神無き世において、神に代わって正義を遂行するのが自分の使命であると、大上段に振りかぶった答えをする。
この後の彼自身とパオラの反応が面白い。父親の前で偉そうな発言をしたブルネッティであるが、さすがに義父の言葉を野気に病み、パオラにその日特に優しい言葉をかける。ところが、いつもの癖で、それはいつしか仕事の話、捜査の話になってしまう。
最終的にブルネッティは妻に、父の言葉を告げるのである。パオラはごくあっさりと、
「それは心理的なおしゃべり症状ね。」
と言ってのける。
「自分自身の問題を、側にいる人間に投影しているのよ。」
つまり、父親は、これまで自分の妻をおろそかにしてきた罪の意識を、自分の妻とその夫に投影しているというである。事実彼女の言う通りなのであるが。ともかく、それまで、実業家の父、警察官の婿の間でギクシャクしていた関係の中に、この巻で何か友情のようなものが芽生え始める。
イタリアらしいと笑ってしまうシーンが今回もある。コートを着て外出しようとしたブルネッティが、外の陽気に気がつき、彼のコートを警察署の受付に預かってもらおうとする。受付の若い警官は、コートをブルネッティの部屋まで持って上がっておくと言う。それに対して、彼は、
「必要ないよ。ここに置いておいてくれればいいから。」
と言う。そのときの、部下の答え。
「お部屋へ持って行かせてください。最近ここでは物がよくなくなりますから。」
「えっ。警察署の受付からかい。」
部下は、警察署の前の、滞在許可を求める移民たちの行列を指し示す。イタリアでは、警察署の中と言えども、決して安心できないのである。これが、真実ではなく、レオンの洒落であることを私は祈る。