�u�[���v�̐��`�v(Selbs Justiz)
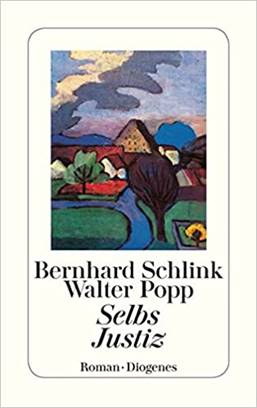
�@
���ƌ����Ă��A���̏����̂ƂĂ��Ȃ����j�[�N�ȓ_�́A
�@�@��l���̒T�オ���A�i�`�X�����̍��ƌ����ł���B
�A�@��l���̒T�オ�Ō�ɂ��Ƃ߂��Ɛl���E���Ă��܂��B���܂��ɁA����͒N������������ꂸ�A�ނ͍߂ɂ�����Ȃ��B
�ȏ�̓�_�ɐs����B�@�͂��悻�A�h�C�c�l�̏����̑P�ʂƂ��Ă̎�l���Ƃ��Ă͈ٗ�ł��邵�A�A�̓A�K�T�E�N���X�e�B�[���u�A�N���C�h�E�l�����v�ŁA�Ɛl�͎��ۂɂ͏����肾�����ƌ����ӕ\�������g���b�N���g������A�u�I���G���g�}�s�E�l�����v�ŊF���Ɛl�������Ƃ�������܂ł̏펯�������������������A����ɗނ�����̂ŁA���悻���������̖��̏���s�����̂ł���Ǝv���B
���̖{�̎�l���A�Q���n���g�E�[���v�͘Z�\���߂����}���n�C���ɏZ�ގ����T��ł���B�ނ͂�����A�c����݂ł���A�`���̌Z��ł�����A�}���n�C���ɂ���傫�ȉ��w��Ђ̎В��A�R���e����葊�k����B�R���e���̈˗��́A�����̉�Ђ̃R���s���[�^�[�V�X�e���Ɂu�n�b�J�[�v���N�����āA�R���s���[�^�[�̃f�[�^������ɏ��������Ă���B���̔Ɛl��˂��~�߂Ăق����ƌ������Ƃł���B���Ȃ݂ɂ��̉��w��ЁARCW�̃��f����BASF�ł���B���ۂɃ}���n�C���A���̑Ί݂̃��[�h���B�b�N�X�n�[�t�F���ł́A���C���͂ɉ����āA���L���ɂ��n��A���̉�Ђ̍H�ꂪ�����Ă���B
�[���v�͑{���̌��ʁA��Ђ̃R���s���[�^�[���L����Q�W���Ď��V�X�e���Ɛڑ����Ă��邱�Ƃɖڂ����A���̒n�������̂̃R���s���[�^�[�Z���^�[�ɋ߂�v���O���}�[�A�~�V���L�[���^���B�����n�b�J�[�͔ނł������̂����A�b���͂���ŏI���Ȃ��B
�~�V���L�[���A�����Ԏ��̂�������ŎE�����B�[���v�͎E���ꂽ�j�̐g�ӂ�����ɁA�푈���̃��_���l�ߗ������J���ƁA���_���l�ɋ��͂����T�{�^�[�W������ĂɊւ��āA��Г��̒N�������ɏo���Ȃ��閧�������Ă���A�~�V���L�[�͂�����l�^�ɁA����l�����������Ă������Ƃ�m��B�[���v�́A�����̐l�Ԃ��A�푈���̎����̔閧�����ɂ��Ȃ����߁A�����Č��݂̒n�ʂ���邽�߁A�����m�����~�V���L�[���E�Q�����Ɗm�M���������B
�Ƃ��낪�A���̃��_���l�����J���ƁA�T�{�^�[�W��������S�����������́A���Ȃ�ʃ[���v���g�Ȃ̂ł������B�ގ��g���A�閧��m�炳�ꂸ�A�N���ɑ����A�x�炳��Ă����̂��B�������āA�����́A�ގ��g���ւ�����ߋ��̏o�����ւƑk���Ă����A�[���v���g����O�҂���A���̉Q���̐l�ԂƂȂ�̂ł���B
�@
�����T��A�[���v�́A�i�`�X����A���ƌ����Ƃ��ăi�`�X�����̋��͎҂ł������ߋ��������Ă��邱�Ƃ͑O�q�����B�ނ́A���̂��Ƃi�͌������Ȃ��̂ł��邪�A�ނ������Ɏv�����Ă��鉻�w��Ђ̔��l�鏑�ɖ₢�l�߂��āA�d���Ȃ������̉ߋ���b����ʂ�����B���̒��ɁA�[���v�́A�Ђ��Ă͍�҃V�������N�́A�i�`�X�����ւ̋��͎҂ɑ��鐳���Ȍ������\��Ă��Ėʔ����B
�u�[���v����͐̌��@��������Ă���ꂽ�����ł��ˁB������ǂ����Ă����߂ɂȂ�����ł����B�v
�Ɣ鏑���q�˂�B
�u�푈�̌�A�N������K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ�����ł��B���͋؋�����̍��ƎЉ��`�҂ŁA�ϋɓI�ȃi�`�X�}���ŁA���i�ȍ��ƌ����ł����B�퍐�Ɏ��Y�����Y���A���ꂪ�ʂ������Ƃ�����܂����B����́A�Ȃ��Ȃ����������̂���R���ł����B���͍��ƎЉ��`�Ƃ���ɂ܂�邱�Ƃ�M�Ă��܂������A�����̗�����ٔ��Ƃ����O���ɗ����m�ł���Ɨ������Ă��܂����B�푈�̖{���̑O���ɂ͉���ׂ̈Ɏn�߂��痧���Ƃ͂ł��܂���ł�������ˁB�E�E�E�v
�u���l�ܔN�̌�́A�悸�A�`���̗��e�̔_��ɐg���A�ΒY�̏����Ȃ�������A�����T��Ƃ��Ă̓�����݂������ƌ����킯�ł��B���@���ɂ�����x���E���邱�Ƃ́A�������̎���ɂ���܂���ł����B���͎����̂��Ƃ����ƎЉ��`�̐��̒��ł����̍��ƌ������ƌ��Ă��܂������A���ۂɂ����ł���A�����Ă���ȏ�̂��̂ł͂Ȃ�������ł��B�E�E�E�v
�@�����āA�ނ́A���̎Ⴂ�l���猩��Ɣn���n���������Ƃ��Ǝv���邪�A�����A�������^���Ƀi�`�X������M�Ă������Ƃ��J��Ԃ��A��㎩���Ȃ�ɐ��Z�͂������A�����̎����̍s�������ł�������Ă��Ȃ��Ɩ������B
���̂悤�Ȑl�����A�P�ʂƂ��āA��l���ɐ����Ă��܂��Ƃ����̂́A�h�C�c�̏����Ƃ��ẮA�ٗ�Ƃ���ƌ�����B�������A�[���v�̉ߋ��ɑ��錩���́A��ʐl�̂���Ɉ�ԋ߂����̂̂悤�ȋC������B
���̏����̓o��l���A�[���v���܂߂āA���ꂼ����ƃ��[���A�ɕx�݁A�ǂ�ł��Ďv�킸���Ă��܂��ӏ��������B
�[���v�́A�X�E�B�[�g�E�A�t�g���ƌ�������̉��������炵�A�T���u�b�J�Ƃ����C�^���A�̎����X���A�I�y���E�J�f�b�g�����A�����ł́u���v�Ȑl�����C����Ă���B�ނ̔Y�݂Ǝ�_�́A�Z�\���߂��āA�V���������ɔۉ��Ȃ��ɔ����Ă��Ă��邱�Ƃ��A�F�߂����Ȃ����A�F�߂���Ȃ����Ƃł���B
�ނ̗F�l�ɂ́A���ꂼ����I�Ȑl�ނ������Ă���B��Ԃ̐e�F�́A�Ō�w�̐K��ǂ����Ƃb��ɂ��Ă����t�A�t�B���b�v�ł���B�ޓ��A���I�ȗF�l���A�A�ɂȂ�A�����ɂȂ�A�[���v�ɋ��͂��āA��₪��������Ă����B
�L���ŁA�Â����o��l���̐ݒ�́A�V�������N�́A���̏������P�Ȃ������ł͂Ȃ��A�l�Ԗ��̂���؏����ɂȂ�悤�ɂƂ����A�H�v�Ɠw�͂̐Ղ��M����B�������A���̌y���l��̂��ӂ�镔���ƁA�d���Đ[����L�̃i�`�X����̕����̍����]��ɂ��傫���A�ǂ�ł��Ȣf�����Ƃ��������B
�Ō�Ɍ����ł���B���̂��l���E����A���̎����O��I�ɒǂ��A�o����A���S�ƍߐ����̒��O�ł���ƔƐl��������B���̔Ɛl���A��l������������E���Ă��܂��A����ɑ��ẮA���S�ƍ߂��������A��l�����߂ɖ���邱�Ƃ��Ȃ��B���̑傫�ȕЎ藎�����A��������Ə����グ���\���Ă��܂����V�������N�B�����܂ōs���Ɖ����ł���A���҂ł͂Ȃ��Ə^�ɒl����ƌ�����̂ł͂Ȃ����B