ゼルプの裏切り」(Selbs
Betrug)
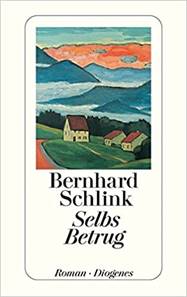
一九九二年に出版された、私立探偵ゲーハルド・ゼルプシリーズの第二作目である。第一作の「ゼルプの正義」は一九八七年に出版されており、前作から五年という結構長い時間が経っている。そして、この書評を書いている二〇〇一年まで、まだ続編は発行されておらず、おそらく、この作品が、ゼルプの登場する二作目にして最終作となると思う。
ゼルプは、政府の要人と名乗る男から、電話で、行方不明になったハイデルベルク大学の女子学生レオノーラ・ザルガーの捜索を依頼される。そして、彼女が、とある精神病院に収容されていたことを突きとめる。その病院の若い医師ヴェントが、彼女を匿い、逃亡させたらしい。ゼルプは更に、医師の身辺を洗い、遂にレオノーラを発見する。ところが、レオノーラを捜しているのはゼルプだけではなかった。警察も、アメリカ軍基地を襲ったテロリストと一人として、彼女を追っていた。そして、ゼルプが彼女の居所をつきつめたと同時に、警察は公開捜査に踏み切る。ゼルプは警察を出し抜き、彼女と会ってその話を聞く。そして、警察の発表と、彼女の話す内容に大きな違いがあること、警察の発表に不自然な点が多いことに気付く。警察に不信感を募らせたゼルプは、彼女の国外逃亡に手を貸す。
彼女のグループが襲撃したのは、毒ガスが貯蔵されているという噂のある、米軍の弾薬貯蔵庫であった。警察の発表によると、彼女が襲撃したとされるのは別の米軍基地である。ゼルプは、毒ガスの存在を隠す為に、警察が、襲撃された場所をすり替えていることを察知する。そして、同じく事件に興味を持つカメラマンと協力し、ドイツ政府の役人と偽り弾薬貯蔵庫を訪れ、内部文書を手に入れ、警察の欺瞞の動かぬ証拠を握る。
しかし、ゼルプは警察から指名手配中の容疑者の逃亡を助けた罪で留置場に入れられてしまう。警察権力との戦いが始まる。
このように粗筋のみを書いていくと、さぞかしスリルとサスペンスに満ちた、手に汗握る筋の展開だと思われるかも知れないが、この小説のもう一つの面は「笑える推理小説」なのである。例えば、ゼルプが、外国人らしい子守り女性が、実はレオノーラだと見破る場面。
彼は行きつけのイタリア料理店で、そこの主人ジョバンニと「イタリアからの出稼ぎ人と話すドイツ人ごっこ」をやる。つまり、本当は、ジョバンニも流暢なドイツ語を話すのであるが、ジョバンニはわざと変なイタリア風のドイツ語を話し、それにつられて自分のドイツ語が変になってしまうドイツ人の役割をゼルプが演ずる。読んでいて、馬鹿馬鹿しいが、これが面白い。しかし、ある夜、ゼルプがその遊びをしかけても、ジョバンニは忙しいのか、乗ってこない。流暢なドイツ語で答える。ところが、ゼルプが「お勘定」を頼むと、ジョバンニは突然、イタリア語で計算を始める。
「あれっ、計算はイタリア語かい?」
ゼルプが尋ねる。
「俺がドイツ語を喋れるのに変かい?でも、数を数える時は、誰でも自分の言葉に戻るもんだ。たとえそれが簡単な計算でもね。」
とジョバンニが答える。この一言がヒントになった。昨日、ゼルプは外国人らしい子守り女性と電話で話した。わざと外国人っぽいアクセントで話してはいたが、彼女は確かに数をドイツ語で数えていた。彼女はドイツ人だ。そして、おそらくレオノーレだ、と言うことが、ゼルプの脳中に閃くのである。読んでいる私も、そう言えば、普段はドイツ語で仕事をしながらも、計算だけは未だに日本語でしている自分に気が付いて、苦笑してしまった。
前作に引き続き、ゼルプを取り巻く人々も多士済済である。前作でゼルプが知り合ったブリギッテは、今回ゼルプの恋人で登場する。彼女はブラジルから分かれた前夫との間にできた息子を引き取り、育てている。ゼルプを始めとする大人達が、その息子のペースに巻き込まれて右往左往する。
これも前作に引き続いて登場の、ゼルプの親友で、看護婦の尻を追い掛け回すことに命を賭けているフィリップ。彼にも遂に年貢の納め時が訪れ、トルコ人の看護婦と結婚する破目になる。しかし、挙式の直前に躊躇した彼は、トルコから招待した親族の一人にナイフで刺されてしまう。
警察の方も、憎めない面々である。警部のネーゲルバッハの趣味は、マッチ棒で、世界中の有名建築物のミニチュアを作ること。これまで、ビッグベン、エッフェル塔、金門橋などを作って、定年退職を待って、バチカンのサンピエトロ寺院に挑戦することを楽しみにしている。
このような憎めない登場人物に、犯罪や国家秘密が絡んでくる。読んでいて、ソープオペラと、犯罪ドラマの融合物を見ているような気分にさせられる。
そして、今回もゼルプは自分がかつてナチスへの協力者だったことにこだわっている。それはそれでよいのだが、彼ば前作で殺人を犯したことに全然こだわっていない。そこが不思議と言えば不思議である。