�u�����������v�iLiebesfluchten�j
�@�����N�ɏo�ł��ꂽ�A�V�������N�̍ŐV��ŁA���̒Z�҂����߂�B�O��́u�N�ǎҁv�ł͂܂��~�X�e���[���ۂ��Ƃ��낪���������A���̖{�Ɏ��߂��Ă���e�Z�҂ɂ͎�ɐl�ԊW���e�[�}�ɂ������̂ł���B�V�������N�͂��̖{�Ŋ��S�Ƀ~�X�e���[��Ƃƌ����g����̒E�p�ɐ������Ă���B����́u�����̗ցv�͂قڊ��S�Ȑ��������A�ƍߏ����ł��������A��i���d�˂邲�ƂɈ�т��ă~�X�e���[�L�������Ă����B�x�X�g�Z���[�́u�N�ǎҁv�ł����A��l���n���i�̓�ɕ�܂ꂽ�ߋ������炩�ɂȂ�ߒ����A�߂炦�悤�ɂ���Ă̓~�X�e���[�ƌĂׂȂ����Ƃ��Ȃ��B�������A���̍�i�Q�͑�ɂ�����悤�ɁA��т��āu���v���e�[�}�ɂ����S�������Q�ł���B
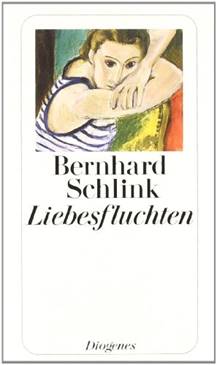
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@***�@
�u�Ƃ������������v�iDas�@Maedchen�@mit�@der�@Eidechse�j
�@
�@�V�������N�̓��ӂƂ���A�i�`�X����̏o�����ƌ��݂𗍂܂�����i�ł���B�܂��A�o��l�������e���ٔ����ő��q���@�w�̊w���B�V�������N�̍�i�̓T�^�I�Ȃ��V���Ă������Ă���B
�ٔ���������Ă��镃�e�̕����Ɂu�Ƃ������������v�̊G���|�����Ă���B���̊G���q���̍����璭�߂Ă�����l���́A���̊G�Ƃ��̒��̏����ɖ������Ă��܂��B�G��`�ʂ���Ƃ����h��ŁA���C�ɓ���̂��̊G�̂��Ƃ����N���������Ƃ������A���e�͘T�����Ă�����~�߂�����B
��������e���ˑR�ٔ��������߂�B�����ȃA�p�[�g�Ɉ����z���A�Ƒ��̕邵�����͈ꋓ�Ɉ�������B�������A���e�͂��̊G�����͎�������Ƃ��Ȃ��B���e�͂��̌��Z��ɂȂ�A�g�̂��Ď��S����B��w�ɐi�݉Ƃ𗣂�Ă�����l���́A���̎��セ�̊G������A�����̏����ȕ����Ɋ|����B
���̌�A���͕��e���A�i�`�X�������ɁA�ٔ����̒n�ʂ𗘗p���āA���_���l����s�@�ɋ��i�������グ�A����Ɋ��Â���������L�߂ɂ����Ƃ����^�f�ŁA�ٔ������Ƃ��ꂽ������m��B���ꂪ�����Ƃ���A��l���̑�D���ȁu�Ƃ������������v�̊G�����A���_���l����D�����u���i�v�Ƃ������ƂɂȂ�B���e�́A�����A�����̂̃��_���l�����e������ɂȂ邱�Ƃ��珕���A���̎ӗ�Ƃ��Ă��̊G�������Ǝ咣���Ă����B
�u���v�͕��e�ƊG�ɂ܂��^����˂��~�߂悤�ƌ��S����B�����āA���̊G�����l�E�_���}���Ƃ������_���n�̃t�����X�l��Ƃɂ����̂ł��邱�Ƃ����Ƃ߂�B�푈�u�����A��ƃ_���}���̓X�g���X�u�[���ɑ؍݂��Ă����B�����āA�����ōٔ��������Ă������e�Ɖ�Ƃ̐ړ_�ɂ��ǂ蒅���̂ł���B
��l���͑傫�������ĎO�̖��ƒ��ʂ���B
�@ ���e�Ɖ�ƂƊG������^���͉����ƌ������B
�A �����ł��킭���G���������Ă��鈳�����B
�B �G�ɕ`���ꂽ�����ւ̓��ہB
��������C�ɉ���������@�����Ɏ�l���͌�����B���ꂪ���̕���̌����ł���B��l���̐N�̈ꖇ�̊G�ɑ��邱����肪�ُ�ɋ������āA�ނɊ���ړ����Ă����ɂ͂�����ƒ�R���������B���݁A���풆�A�h�C�c�l�����_���l����D�����G��A�����̎�����A���̎q���ւ̕Ԋ҂����������Ă���B���݁A�ꖇ�̊G�ƌ����ǂ��A���ꂪ�푈�ƊW����ƁA�܂��܂��ߋ�����������h�C�c�l�ɂ́A�Ȃ��Ȃ������Ȋӏ܂̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��낤�B
�@
�u�������сv�iDer�@Seitensprung�j
�@�h�C�c�l�́A����E����A�i�`�X�����̕���ɂ��A����܂ł̉��l�ς��ꋓ�ɕ���Ƃ����J�ڂɉ�����B�����h�C�c�̐l�B�͂���ł��܂������B�����肾��������B�������A�����h�C�c�̐l�����́A����ɂ�����x�A��������̍ہA����܂ł̎Љ��`�ɍ����������l�ς̕���Ƃ����h���ڂɉ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�\�N�Ԃɓ�x���A�܂�ꐶ�̂����ɓ�x���A����܂ł̍s����A���l�ς�ے肳���A����͑��߂���Ǝv���B
���̓�x�ڂ̉��l�ς̕���A���h�C�c�̕����w�i�ɂ��̕��ꂪ�W�J����B����v�w���ϊv�̍r�g�ɝ��܂�āA���̒��Ŏ����B�̖ڎw�����̂�͍�����ߒ����A�u���v���痈������A�u���v�̖ڂ�ʂ��ĕ`�����B�����g�A�x�������̕ǂ̕���A�����h�C�c�̓���A����������A�̗��j�I�ȏo�������h�C�c�ɂ��đ̌�����Ƃ����K�^�Ɍb�܂ꂽ�B�u�����h�C�c�̓���v�ƌĂԂ̂͐������Ȃ��B�u���h�C�c�ɂ�铌�h�C�c�̕����v�ƌĂԂׂ��ł���̂����B�Ƃ������A���̂Ƃ��ł����A�u���v�̐l�ԂɂƂ��āA�u���v�̐l�Ԃ����̕ω����ǂ̂悤�Ɏ�e���Ă��������͓�ł������B���̓�̈ꕔ���������������悤�ŁA���̕���͋����[���B
����ł���u���v�͓�������O�Ɏ����̏Z�ސ��x���������瓌���֗V�тɍs���A�����ł���u���v�̉Ƒ��ƒ��ǂ��Ȃ�B�v�ł���X���F���ƍȃp�I���́A��������̌����̎�����A�I�݂ɏ���A�u���v�̐l�ԂƂ��Ă͒����������҂ƂȂ�B�v�A�X���F���͑傫�ȉƁA�����Ԃ����߁A���������ɗ��s�ɏo�����A�����I�ɖ�������邱�ƂōK����������B
�Ƃ��낪�A�v�����āu�V���^�[�W�v�i���h�C�c���ƕۈ��ǁE�閧�x�@�j�ւ̓��ʎ҂��������Ƃ��A�Ȃ͒m��B����ꂽ�Ɗ������Ȃ́A�v����w�̏���t�ɍ̗p���ꂽ���A���̏j���̐ȂŁA�v�̌��𗣂�錈�S���A�u���v�Ɠ��̊W�����B�������A���̌�A�v���閧�x�@�ɓ��ʂ����̂́A�f���ɎQ�����đߕ߂��ꂽ������������ׂ��������Ƃ��m��B
�薼�́u�������сv�Ƃ́A����܂ŕ���ł��������̂āA���ɂ���ʂ̓��ɂ҂��Ə�芷����ƌ����Ӗ��Ŏg���Ă���B�v�̃X���F���́A�|��Ƃ���s���^���ɓ]���A�閧�x�@�̓��ʎ҂ƂȂ�A�����͑�w�ɐE��B�����̐������A���l������̂Ƃ����̂Ƃ��ɉ����čI�݂ɕω������Ă������Ƃɂ��A�u���v�̐l�ԂƂ��Ă͗�O�I�Ȑ��������߂�B�������A�Ȃ̃p�I���́A�ꏏ�ɔ�ׂȂ��̂ł���B�v�̍s��������܂ŁA�s�������ɂ��Ă������Ԃւ̗���ł���Ɣ���B
�����ɂ͊����ď����Ȃ����A�Ō�ɂ��̕v�w�̂��ǂ蒅����́A���Ắu���v�̐l�X�̍ł���ʓI�ȋA���������Ă���ʔ����B�u�ߋ��̂��Ƃ͂����猾���Ă����������Ȃ��A�Y��܂��傤�B�������������Đ����Ă����܂��傤�B�v�ƌ������ƂɂȂ邾�낤���B
�h�C�c�ł́A���݂��A�������̎Љ��`�̐��̒��ł̔ƍߍs�ׁA�Ⴆ�x�������̕ǂł̖S���҂̎ˎE���ɑ��čٔ����s���Ă���B�܂��A���Ă̔閧�x�@�̋��͎҂ł��邱�Ƃ�������ƁA�Љ�I�Ȓn�ʂ���Ԃ܂��B�i�`�X��������̌�n���Ɠ������A�ߋ��͂���Ȃ�ɐ��Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����A�h�C�c�l�̍D���Ȍ��O�_�ł���B�������A��ʂ̑�O�͂����ƕʂȌ`�ʼnߋ����������Ă��邱�Ƃ��������Ă����i�ł���Ǝ��͎v���B�@
�u������l�̒j�v�iDer�@Andere�j
�@
�������N�ސE����������̎�l���A�u���v�̍ȁA���U���a�C�ŖS���Ȃ����B�������ς܂��A��l����ɂȂ����₵���ɑς����˂Ă���Ƃ���ɁA����j����莆���Ƃǂ��B�莆�̓��e����A���o�l�́A�o�C�I�����t�҂ł������ȂƐ[���W�ɂ��������Ƃ��@����ꂽ�B�u���v�͍Ȃ�����u������l�̒j�v�̑��݂ɜ��R�Ƃ���B�����Ă��̒j�Ɏ��̂悤�ȕԐM�������B
�u���莆�q���������܂����B���������Ȃ��̎莆�͂���]�̏����ɂ͓͂��܂���ł����B�M���̒m���Ă��郊�U�A���Ȃ��̈��������U�͂��̐��ɂ͂���܂���B�@B���v
�Ƃ��낪�A�����́uB�v�����R�A���āu������l�̒j�v�����U���ĂԎ��Ɏg���Ă������̂̃C�j�V�����ƈ�v���Ă��܂��B�j�͎莆��������A���U�������Ƃ�M�����A�X�Ɏ��̂悤�Ȏ莆�������B
�u�����銌�F�̓���B���܂��͎��̈��������̃��U�ł��肽���Ȃ��ƌ����̂��B���U�͎��ׂ̈Ɏ���ł��܂����ƌ����̂��B
�ߋ��̏o�������v���N�������Ƃ����݂̂��܂��ɋ�ɂł��邪���߂ɁA�ߋ��𑒂苎�肽���Ƃ����C�����͂悭�킩��B���������̉ߋ����܂����܂��̒��ɐ��������Ă��邩�炱���A���݂̂��܂��ɉe����^���Ă���̂��B����ꂪ�ꏏ�ɉ߂������ߋ��́A���̐S�̒��Ɠ����悤�ɁA���܂��̐S�̒��ɂ����������Ă���B����͑f���炵�����Ƃ��B�܂��A�������̎莆�ɑ��ĕԎ�������Ȃ��������܂����A����ւ�����ꂽ�A������f���炵�����Ƃ��B�����āw���F�̓��x�Ƃ������̂����Ăі����C�ɓ����Ă���āA���̃C�j�V�����́wB�x���g���Ă��ꂽ���Ƃ��B
���܂��̎莆�͎����K���ɂ��Ă��ꂽ�B
�����t���v
�u���v�̏������莆���B���Ȃ�A���́u������l�̒j�v�����t�̑��Ƃ�����ɒ[�ł���B�u���v�͎��Ȃɐ�������āA���̒j�ƕ��ʂ�����j�ڂɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ����Ȃ�̑�������̒j�ɒ��������Ƃ����A�{��S���ɔ������u���v�́A���́u������l�̒j�v�ƑΌ����ׂ��A�j�̏Z�ޒ��ւƌ������B�����āA�i���X�Œj�ƃ`�F�X�̔Ղ��͂ނ��Ƃɂ��A���悢�悻�̒j�ƌ��t�����킷�@������̂ł���B
�@���̌�A�u���v�����̓��U�̕v�ł���ƋC���t���Ȃ��j�Ɓu���v�̊ԂŁA��ȊW�����܂��B�����Ă��̒j�̐��̂����X�ɖ��炩�ɂȂ��Ă����B�u���v�͂��̒j�ɑ��A���Q�̋؏��������A��������s���Ă����̂ł���B
�@��l�̏����̎�������b�ł��邪�A����͊쌀�ł���B�����̍Ȃɐ������A�Ȃ̂��Ă̗��l�Ǝv����j�ƕ��ʂ��Ă��܂��A����ɑ�����C�����Ȃ��Ƃ����s���R���͂���B���̕s���R���̏�Ō��킳����l���Ɓu�����ЂƂ�̒j�v�Ƃ̉�b�͏���U���B�ϋq�̂����m���Ă��鎖���ɓo��l�����C�����Ă��Ȃ��ŁA�Ƃ�ȉ�b���J��Ԃ��A�ϋq�̏���U���ƌ����̂́A���{�́u�Ȃ�Ƃ��V�쌀�v�ɂ��p�ɂɓo�ꂷ������ŁA�쌀�Ƃ��Ă͂��Ȃ�ÓT�I�ȋZ�@�ł��낤�B����Ȃ�[���ȑ�ނ��������Ȃ���A�����i�Ɏd�グ�Ă��܂��A�V�������N�̓��ӋZ��������Ȃ���������Ă����i�ł���B
�@�������A�Ō�Ɂu���v���u�����ЂƂ�̒j�v�ɉ��ƂȂ�����ǂ��납�F��������Ă���悤�Ɏv���̂́A�[�ǂ݂̂��������낤���B
�������iZuckererbsen�j
�@�M�҂ł��鎄�͂��鏗�����D���ɂȂ�ƁA��x�Ƃ��̐l�������ɂȂ�Ȃ��B�����A����܂ōD���ɂȂ��������Ƃ̊W���S�ăn�b�s�[�G���h�ɏI���킯���Ȃ��B�ʂꂪ����B�����҂ǂ��U��ꂽ���Ƃ����x���������B�������A����ł����̏����������ɂȂ�Ȃ��B���̏��������V���Ȓj���ƕt�������n�߂Ă��A���邢�͌������Ă��A���܂ɂ͉���Ęb�����Ă݂����Ǝv���B�j�ƌ������̂́A�����̑O�ł͉����ۂ̈����A�D�_�s�f�Ȑ������Ȃ̂ł���B
�@���̈Ӗ��ŁA���̕���̎�l���ł���g�[�}�X�ɂ́A���ƂȂ�����ړ����ł���B�x�������ɏZ�ތ��z�Ƃł���ނ́A�ŏ��ɓ����ł��郆�b�^�ƒm�荇����������B�����ē�l�̎q����݂���B�K���ȉƒ�ł���B���̌�A�ނ͗���Ńn���u���N�̉�L�̌o�c�҃��F���j�J�ƒm�荇���B�ޏ��̓g�[�}�X�̊G�̍˔\���������A�ނ���ƂƂ��ăf�����[������B�g�[�}�X�̓��F���j�J�ƈ��������悤�ɂȂ邪�A�Ȃ̃��b�^�ɂ͕ʂ�b���o���Ȃ��܂܁A���邸��Ɠ�l�Ƃ̊W�𑱂��A�x�������ƃn���u���N�ł̓�d�����𑗂�B���ɂ��̓�d�����̏d���ɑς����Ȃ��Ȃ�A�ނ͗F�l�ƎR�����ɏo�����邪�A�����ŏ��q�w���̃w���K�ƒm�荇���A���̊W�����B���ɖ߂��Ă����Ƃ��ɂ́A��d�����ǂ��납�A�O�l�̏����ƕt������Ȃ���Ȃ炢��ԂɊׂ�B��ɁA����ł͂����Ȃ��Ǝ��Ȃ̔O�ɂ����Ȃ�����A���z�ƂƉ�ƂƂ��ĎЉ�I�ɐ������Ă���A���ꂪ�o�ϓI�ɂ͋������ނɂ́A���̐������猈�ʂ��铥��肪���Ȃ��B�܂����邸��ƎO�l�ƊW�𑱂��Ă����B
�@�j���[���[�N�ɏo�������ۂ̃G�s�\�[�h�͖ʔ����B�G�t�����O�������A�O�l�̏����Ɉꖇ�������n�߂�B�����C�̕��������Ƃ������˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ȃ�����A�ŏI�I�ɎO���Ƃ��u�h�C�c�ɖ߂����炨�܂��ƈꂩ���蒼�����v�Ə����Ă��܂��̂ł���B
�@���̐����̏I���́A�ނ��K���Ɛf�f���ꂽ���ɗ���B��҂ǂ��납�O�҂�������Ƃ����A����ΎO�l�̏��������ɂЂǂ��d�ł������Ă����ނł��邪�A�]�����������Ɛf�f���ꂽ�����ɑ��āA�O�l�Ƃ����₩�ȓ_�ɁA�������āA����܂ł̎����ɔ��Ȃ�����B�d���ĉ��őm�������炦���g�[�}�X�͂́A������܂Ƃ��A���Q�̗��ɏo��B
�@�����͂��Ȃ�A�����J�̊쌀�f��I�ł���B�O�l�̏����́A�ނ��l���Ă������͂邩�ɂ��������ł������B�Ⴆ���b�^�́A����܂Ńg�[�}�X���ʂ�b���o�����Ƃ���ƁA�����I�݂ɘb�����点�Ĕނɂ���������Ȃ������B����́A�ꌩ�����Ƃ̑Ό�������悤�Ƃ���ޏ��̎コ�Ǝv�킹��̂ł��邪�A�ǂ������A����͍I�݂Ȍv�Z�̏�Ȃ̂ł���B�_�ɏ���Ăǂ��܂Ŕ��ł��A���ǎ߉ނ̎�̒����瓦���o���Ȃ����������̈�b�̂悤�ɁA�g�[�}�X���O�l�̎�̒��ł������Ă����悤�Ȃ��̂������B���̕�����쌀�Ƃ��Ė������B
�@�u�������v�ƌ����^�C�g���A����͎�l���������I�Ȗ�S���̂ĂāA�����I�ȉ��l�ςɓ��邱�Ƃ𝈝����Ďg���Ă���̂����A���S�ɂ͂��̈Ӗ���������Ȃ������B
����iBeschneidung�j
�@�ŋ߁A��Z�Z��N�ɂȂ��Ă悤�₭�A����E��풆�̃i�`�X�������ɂ�����A���_���l�̋����J���ɑ���⏞��肪���������B����̕⏞�����}���˂Ȃ�Ȃ����R�ɁA�����҂�������Ă���A�⏞�����Ɏ���ł����l���ǂ�ǂ��Ă����Ƃ������Ƃ��������B���̕⏞���́A����ŁA���\�ܔN�ȏ�o���������A�����̃��_���l�s�҂̋L���́A�h�C�c�l�ƃ��_���l�݂̂Ȃ炸�A���E���̐l�X�̐S�ɍ����Ȃ����܂�Ă��邱�Ƃ�\���Ă���B�܂��A��������ł́A�����̒��ڂ̉��Q�ҁA��Q�҂��c�菭�Ȃ��Ȃ�A���̐��オ�命�����߂��邱�Ƃ�\���Ă���Ǝv���B�@
�h�C�c�l�ƃ��_���l�B���Q�҂Ɣ�Q�ҁB�������̖����͂��̎�����w�����Đ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤���B�h�C�c�l�Ɍ����Č����A�푈�̍ۂɐ��܂�Ă����Ȃ���������ɁA�܂��i�`�X�������h�C�c�l���s�����s�ׂɑ���ӔC������̂��낤���B
�h�C�c�l�j���A���f�B�ƃ��_���l�����̃T�[�������ɗ�����B�ŏ��A�A���f�B���T�[���̐e�ʂɏЉ��A���ɂ̓T�[�����h�C�c�ɏ��҂���A�A���f�B�̐e����F�l�ɏЉ���B�Љ����͎����̐e�ʂ�F�l���������Ȃ��Ƃ�b���o���₵�Ȃ����ƂЂ�Ђ₾���A�Љ�������A�����̌�����������̋C�����Q���邱�ƂɂȂ�Ȃ����Ђ�Ђ���́B�ْ��̘A���ł���B
�ӂ���̊Ԃ��A���̘b��͏o���Ă͂����Ȃ��Ƃ����^�u�[�����݂��A���ƂȂ��������Ⴍ�������̂ɂȂ�B�h�C�c�̃}�X�R�~�ɂ́A���̎�̃^�u�[�����������݂���B����A���Ă����B�u�h�C�c�l���푈���ɍs�����s�ׂɂ��ẮA���Ȃ̕ق��q�ׂ邾���ŁA�J�������Ă͂����Ȃ��v�Ƃ��A�u�e���r�h���}�Ń��_���l�����҂ɂ��Ă͂����Ȃ��v�Ƃ��B���̃^�u�[���F�����ƂȂ�����A���ꂪ�h�C�c�l�̋`���ł���悤�Ɏv���Ă���B
���āA�h�C�c�l�ƃ��_���l�̂ӂ���̊W�����A���ǂ̂Ƃ���A�����I�Ɍ����ĉ��Q�҂ł���A�j���ł�����A���f�B���܂��B�ނ́A�J�g���b�N����v���e�X�^���g�ւ̉��@���ł���悤�ɁA���̏@�����烆�_�����ɉ��@���\�Ȃ̂��낤�ƍl����B�����ŁA���̏����̃^�C�g���ł���A���_���l�Ɠ��̋V�������y�����̂ł���B�ʂ����āA�����������_���l�ɋA�����邱�ƂȂlj\�Ȃ̂ł��낤���B
���l�̈ӌ��ł��邪�A��������@�����A������̉��@�҂����ނȂ�A����͂����u�@���v�Ƃ͌������A�P�ɂ��̖������L�́u�y���M�v�ł���Ǝv���B
���̏����̑��郁�b�Z�[�W�́A�ȉ��̃T�[���̌��t�ɋÏk����Ă���Ǝv���B
�u�b�����Ƃ��~�߂Ȃ��ŗ~�����́B�v
�ƃT�[���������B
�u�ǂ����āH�v
�ƃA���f�B�͐q�˂�B
�u���Ȃ����A���̓��̒���ʂ�߂��邱�Ƃ����ł��邩�������Ă��āA���ɂ��Ă��������m�邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���Ă��邩���B�ł��A�������͓�̑S�R����������������Ă��邵�A����܂œ�̑S�R��������t��b���Ă����̂�B���Ƃ����Ȃ����h�C�c�ꂩ��p��ɏ��ɖ|���Ƃ��Ă��B�܂�A�������͕ʂ̐��E�ɐ����Ă���́B�������݂��ɘb�����Ƃ��~�߂���A�ӂ���͖{���ɕʂ�ʂ�ɂȂ��Ă��܂���B�v
�{���̗����A�{���̗Z�a�̂��߂ɂ́A�₦�Ԃ̂Ȃ���b���K�v�Ȃ̂ł���B���̂��Ƃ͉����������ԁA���@���Ԃ̗Z�a�̂��߂����Ƃ͌���Ȃ��Ǝv���B�v�w�ɂ����Ă��A��Ђɂ����Ă��A��b���₳�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���܂ꂽ���Ԃ��A����������Ⴄ�l�Ԃ��A���i�����܂�����Ă����錍���Ǝv�����B
���q�iDer Sohn�j
�@���̕����ǂ�ł���Ƃ��A�M�҂͂��傤�Ǒ��q�Ɠ��{�𗷂��Ă���r���������B���͂܂��܂��e�Ɉˑ����Ă��鑧�q�ł��邪�A�\�N��ނ��Ƃ��o�āA�Ɨ������Ƃ��ɁA���e�Ƒ��q�̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��낤���B�ӂƂ���Ȃ��Ƃ��l�����B�����āA���������ʂƂ��A���q�̂��Ƃ��ǂ̂悤�Ȋ���ł����Ďv���o���̂��낤���B����Ȃ��Ƃ��v���Ȃ���A���̕���̌�����ǂ�ł���ƁA�܂��o�Ă����B
�����̑�����Ă̂��鍑�֒��Ď��c�Ɏu�肵�h�����ꂽ�h�C�c�l�̒j�B���̍��ɓ������������A���{�R�̏��Z�Ɣ����R�̑�\�A���т���̃J�i�_�l�̓����ƁA�W�[�v�ɕ��悵�A���������̎����̒n��������B�ނɂ͗����o��������A���̍ۂ��Ă̍Ȃ̌��Ɏc���Ă������q�ɑ��Ă���܂ł����߂̈ӎ��ɂ����Ȃ܂�Ă����B���̑��q���A��w�𑲋Ƃ��A��҂̗��Ƃ��āA�a�@�œ����n�߂��B�O�鑧�q�ɓd�b���������̂́A������u���̒m�点�v�Ƃ����������낤���B
����ނ̖����́A���{�R�Ɣ����R�̊Ԃō��ӂ��ꂽ��틦����Ď����邱�Ƃł���B�������A���s���鐭�{�R�Ɣ����R�̑�\�̉�b�A������̗l�q���ώ@���A��l���͌��݂̒��A���a�̑��݂ɋ^�������n�߂�B���̗\���͓I�����A���̖�A�h�����Ă���ꏊ�͉��҂��ɏP������A�Ԃ��j��A���l���ł�B��l���́A���̐퓬�ɂ��₨���Ȃ��Ɋ������܂�Ă��܂��B
�������ꂽ�ٍ��̒n�ŁA�s�{�ӂȂ��玀�ȂȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��A�v�������ׂ邱�Ƃ͉��Ȃ̂��B�Ⴆ�A��s�@���ė����āA����������Ȃ��ƕ��������Ƃ��A�Ō�ɐl�Ԃ��S�Ɏv�������ׂ�̂́E�E�E��͂�A�Ƒ��̂��ƂȂ̂��B
�K�\�����X�^���h�̏��iDie Frau an der Tankstelle�j
�����ǂ����Ō������i�Ȃ̂����A���ǂ��Ō��������ǂ����Ă��v���o���Ȃ��B�悭�悭�l���āA������A����͂��Ė��Ō������i�������Ǝv���o�����Ƃ��������B
�܂������̗]�k�ł��邪�A����܂Ŏ��̌�����ԕ|�����B����͎l�A�܍˂̂Ƃ��Ɍ��������B�Ƒ��ŗ��s�ɍs���ė��قɔ��܂�B�嗁��֍s���āA�q���̎�������ɕ����֖߂�B�����ɂ͊��ɕz�c���~���Ă���B���̕z�c�̏�ŁA���낲�낵�Ă���ƕ����̌˂��J���B�����A�ꂩ�A�o���ȂƎv���Ă�������݂�ƁA��F�̈����A����U�藐�����Ⴂ�����������Ă���̂��炻���ɂӂ�ӂ�Ɠ����Ă���B���̏����͎��̖����܂ŗ���B�����Ă����ł��Ⴊ��Ŏ��Ɋ���߂Â���B�����Ŗڂ��o�߂��B
���N��L�����ǂ����։Ƒ��ŗ��s�����Ƃ��A�����ֈē�����āA�u������B�����ǂ����Œ������Ƃ�����B�v�Ǝv�����B�����āA���ꂪ���̒��ŎႢ�����Ɖ�����������Ǝv���o�����B���̖�A�嗁��֍s������A�ЂƂ�ŕ����ɖ߂�Ȃ��������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�b�͂��ꂽ���A���̕���̎�l���̌J��Ԃ����閲�́A���ԓI�ɂ����ƒ����B���N�̂Ƃ�����A��N�ސE��ڂ̑O�ɂ������݂܂ŁA�J��Ԃ������������Ă���Ƃ����B����́A�Ђ�����^�������Ȑl�C�̂Ȃ����H���Ԃő���A�l�����ꂽ�K�\�����X�^���h�ɓ���B�����ŋ����̂��߂ɏo�Ă��������Ɨ��Ɋׂ�A���̃K�\�����X�^���h�ŕ�炷���ƂɂȂ�Ƃ������ł���B
��N�ސE���Ď��Ԃ��ł����j�́A�Ȃƈꏏ�ɃA�����J�嗤�𗷍s����B���C�݂��J�i�_����Ԃœ쉺���A���O���ɓ���B�����āA�l�����ꂽ�C�݉����̓��H�𑖂��Ă���Ƃ��A�I�Ɏ���������܂ʼn��S��Ɩ��Ɍ������i�Ƒ�������̂ł���B�K�\�����X�^���h�ɓ���A�����̂��߂ɏ�����������o�Ă���B���̂������܂ŁA���o��������B�����A���̌�A�j�͖��̒��̂悤�ɁA���̃K�\�����X�^���h�ł��̏����ƕ�炷���ƂɂȂ�̂��낤���B�ǂ�ł��āA���̏u�Ԃ̋̓W�J�ɉ��Y���u�Ԃł���B
���̕���ɓo�ꂷ���v�ȏ����͂������u�K�\�����X�^���h�̏��v�Ȃ̂ł��邪�A�ޏ��͌���Ζ��̒��̓o��l���A���̂̂Ȃ��ے��I�ȑ��݂ɉ߂��Ȃ��B����ȏ�ɋ����������̂���l���̍Ȃł���B�ޏ��͈�҂ł���A����܂ł��̐E�ƂŐ��������߂Ă����B��l���v�w�����N�ɂȂ�A���͂₨�݂��̃Z�b�N�X�ɋ����������Ȃ��Ȃ�B���钩�A�ڂ��o�߂��Ƃ��A�ނ͎����̍Ȃ̘V�X�ƁA�����̏L�A�ޏ���ꍂɑς����Ȃ��Ȃ�f���Ă��܂��B����Ɠ����`�ʂ��u�N�ǎҁv�̒��ɂ�����B��l���̃~�q���G�������Ă̗��l�n���i���Y�����ɖK�˂��Ƃ��A�n���i�̑̂��甭����V�l�Ɠ��̓����ɜ��R�Ƃ����ʂł���B�Ƃ������A�̂���̓����̕ω��Ƃ����̂́A�l�̘V��������������傫�ȗv�f�ł���B�����̍Ȃł��v�ł��A���l�ł��A���̓����������邱�Ƃ͌����ȊO�̉����ł��Ȃ��B������u���ꂢ���Ɓv����ׂĂ��A�����瑊��������Ă��Ă��Ă��A���Ȃ��������Ɋ����Ă���ɂ́u�������v�ł���ƁA�V�������N�ɂ܂������ŔF�߂����Ȃ����Ƃ��A�F�߂������Ă��܂����C�������B