ゼルプの殺人(Selbs Mord)
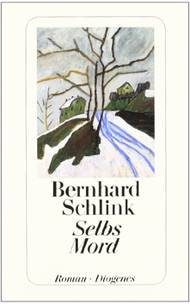
シュリンクの「ゼルプの裏切り」(Selbs Betrug)が出版されたのが一九九二年。同シリーズの続編はもう出ないものと思っていた。ところが、九年後の二〇〇一年九月、「ゼルプの殺人」(Selbs Mord)が発行されたという知らせを聞いた。正直驚いた。シュリンクの作品、特にゼルプのシリーズは、どれも過去の歴史的な出来事と絡めてあるため、時代背景が重要な要素となる。タラちゃんがいつまでたっても小学校に進まない「サザエさん」のように、登場人物がいつまでも歳を取らないことは、このシリーズに対しては許されない。前作は一九九二年で、既に主人公の私立探偵ゼルプは六十歳を越えていた。今回は、クリントン大統領が再選された年、つまり一九九七年を舞台にしているが、ゼルプは既に七十歳を越えた設定になっている。
今回の作品で、作者が描きたかったものは、第一に、東西統一の後今なお続く「東」の人間(Ossi)と「西」の人間(Wessi)の軋轢であると思う。しかし、私は、人生の黄昏を迎えた人々の悲哀を一番に感じてしまった。
幕開きは病棟である。ゼルプは心臓を病み、入院している。病院を抜け出し、事件の現場に向かう。そこで回想される形で、物語が進行する。
ゼルプはある雪の日、雪の中で立ち往生している車を助ける。車に乗っていたのは、地元の銀行の社長ヴェルカーである。ゼルプが私立探偵であることを知ると、ヴェルカーは依頼したいことがあるので連絡を取ってくれるように頼む。
数日後、ゼルプはヴェルカーを彼の銀行に訪ねる。奇妙な点がある。それはヴェルカーの運転手兼秘書のサマリンの態度が異常に横柄で、社長のヴェルカーでさえ、彼に遠慮しているように見える点である。ヴェルカーは二年前に妻を失っていた。妻は、山で遭難して行方不明になったが、死体は見つかっていない。
また、ヴェルカーの依頼事態も通常のものではない。前世紀の末、つまり一八七〇年代、ヴェルカーの曽祖父の時代に銀行が経営危機に陥ったとき、出資してくれ、銀行を危機から救ってくれた匿名の出資者が誰であるか突き止めて欲しいという依頼である。
ともかく、依頼を受けたゼルプは、法学士の卵のゲオルグを捜査のために匿名の出資者の出身地と思われるシュトラスブールに派遣し、自分は、定年退官した教師で、地元歴史の研究家のシューラーを訪れ、情報を得る。(このシューラーがもう老醜そのものの、臭くて汚い爺さんなのである。)
そのシューラーが交通事故でゼルプの目の前で死亡。それも大金の入ったスーツケースをゼルプに託した直後に。そして、ゼルプ自身も何者かに尾行される。尾行者は二組。ロシア人マフィアっぽい男たちと、服装の趣味の悪い中年男である。
ゼルプはヴェルカーの経営する銀行が、東西ドイツの統一の後旧東側の銀行を買収した後、突然金回りが良くなったことに不審を抱く。コツブス市にあるその買収された銀行を訪れたゼルプは、銀行が旧東側の銀行を窓口に、ロシアからの非合法な金を運用することにより不正な利益を上げていることをつきとめる。
ヴェルカーを問い詰めたゼルプは、運転手兼秘書のロシア人サマリンが陰で銀行の経営を操り、不正は全てサマリンのアイデアであること。ヴェルカーは子供を人質に取られていることにより、サマリンの言うなりになっていること、等の告白を受ける。また、行方不明の妻もサマリンに殺害されたと言う。ゼルプは友人のフィリップ、定年退官した元警察署長のナーゲルバッハ等、いつもの仲間の協力で、サマリンを捕捉し、ヴェルカーの子供たちを取り戻すことに成功する。いや、成功したかに見えた。ところが、まだ残りページは百ページ以上ある。さあどうなるのだろうか。
老いというテーマが常に見え隠れする。自分の老いに対して、ゼルプは女友達にこう告白する。(第九章)
「あなたは若い自分に憧れを持っているのね。若くて、強くて、何でもできた時代に。」
とゼルプは問われる。
「何でもできたって。戦争中にはできなくて、戦争が終わってからは完全にできなくなった。年のせいだと思うかい。皆がそう望むように仮に自分がもう年寄りだったとしても同じだ。昔はある日突然老いが始まり、数年後には年寄りが出来上がると思っていた。しかしそうじゃない。老いというものは常に進む。きりがないのだ。」
とゼルプは答える。老いというのは本人がどれほど否定しようと、石を穿つ水のようにどんどんと体を蝕んでいく。留まるところがないものである。
ゼルプはベルリンでネオナチの若者に捕まり、無理やりに「ハイル・ヒットラー」と叫ばされて、挙句の果てに川の中に投げ込まれてしまう。
「私はこれと言う怪我もしなかった。川に落ちたとき、体の水とぶつかった方が翌朝に青い斑点になっていた。鼻水が止まらず、少し熱もあった。しかし本当の苦痛は別にあった。正しく行動しなければならないあのとき、私は間違った行動を取った。一度あることは二度ある。そして今度もまた間違った行動を取ってしまったのだ。」(第十八章)
「あとのき」とはナチスが政権を握った時である。ゼルプは国家検事として、ナチス政権に協力してしまった。「ハイル・ヒトラー」と叫んでしまったのである。そして、今回も、ネオナチの脅しに屈して同じことを叫んでしまった。ゼルプの世代は常にこの後悔と自責の念を持ちながら、死ぬまで暮らしていくのであろう。これまでの、二作で、ゼルプがナチス政権への協力者であったことを後悔していないと述べているのと対象的である。
更に特筆すべきは、第一作で、ゼルプが崖から突き落として殺した、義理の兄弟であり殺人事件の犯人であるコルテンに対して言及すること。今もその幻影に悩まされていることが暗示されれている点である。
異常の二つのエピソードは、やはり老いと迫り来る死を前に、ゼルプが本音のそのまた本音を吐露したと考えていいのではないか。
過去二作は笑える推理小説として特筆に価した。今回も、笑えるエピソードが散りばめらられている。しかし、前作のように素直には笑えない。年老いて、死期が近い喜劇役者の、最後の舞台を見るような、鬼気迫った迫力を感じ、とても単純に笑っておれない気分になるのである。「男はつらいよ」の最終作をご覧になった方は分かるであろう。いつもの筋立てではあるが、見ている者には主演の渥美清が病んでおり、死期が近いことが分かっている。私は、その死の影が見え隠れして、とてもこれまでのように腹を抱えて笑えなかった。同じことをこの作品からも感じた。
ゼルプのシリーズはこれでお終い。もう続編がでることはないであろう。恋人のブリギッテと七十歳を越えて結婚したゼルプのその後、マッチ棒細工のナーゲルバッハが定年後の目標、ヴァチカンのサンピエトロ寺院を完成させるかどうか、友人の外科医フィリップが爺さんになってもまだ看護婦の尻を追い回しているか、知りたい気がするけれども。