「階段の上の女」
Die Frau auf der Treppe
2014年
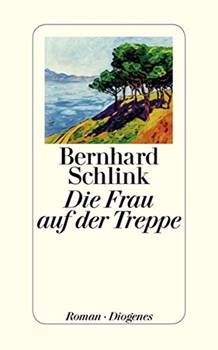
<はじめに>
この話はフィクションであるが、このストーリーの発端となった絵、「階段の上の女」は実際に存在する。ゲルハルト・リヒターという画家が描いたもの、シュリンクはその絵にインスピレーションを得て、この物語を書いたという。

<ストーリー>
二〇一〇年、シドニー
ドイツ人の弁護士である私は、オーストラリア、シドニーでの出張を終え、フランクフルトへ向かう飛行機による予定であった。まだ半日ほど時間があったので、私はサウス・ウェールズ美術館に足を向けた。そしてそこで四十年ぶりに「あの絵」と出会った。それはカール・シュヴィントいう画家の描いた、全裸の若い女性が階段を降りる絵であった。
一九六八年、フランクフルト
「私」は新入りの弁護士として、フランクフルトにある弁護士事務所で働き始めた。若くして優秀な成績で司法試験を合格した「私」は、最初検察官になろうと考えたが、先輩の検察官に説得され、弁護士事務所に勤めるようになったの。そんなとき、現れた依頼者が、カール・シュヴィントであった。先輩の弁護士が誰も興味を示さないので、その件が「私」に回ってきたのであった。シュヴィントは三十歳前後で画家と名乗った。かれには二十歳くらいの若い女性が付き添っていた。
シュヴィントの依頼とは次のようなものであった。シュヴィントはペーター・グンドラッハの注文で、グンドラッハの妻イレネの絵を描いた。その絵はグンドラッハに買い取られて、今はグンドラッハの家にある。カタログに乗せるこれまで描いた絵の写真を自動車事故で失ったシュヴィントは、グンドラッハに絵を撮影することの許可を求めた。しかし、グンドラッハはその依頼に、返事をよこさない。それで、弁護士から写真殺絵の許可を依頼してほしいというものであった。「私」がグンドラッハに手紙を書くと、グンドラッハは快く写真撮影を許可した。
数日して、シュヴィントがまた血相を変えて「私」の事務所に来た。前回と同じ若い女性が付き添っている。シュヴィントがグンドラッハの家に行き、写真を撮ろうとしたところ、絵が傷つけられていたという。それも事故や不注意による傷ではなく、女性胸の部分に薬品がかけられていた。その修理をしたいとグンドラッハに連絡したが、また返事が得られないという。私は再びグンドラッハに手紙を書く。グンドラッハ、絵の傷は画家の不注意によるものであると言う。しかし、シュヴィントが自分の家に来て、その傷を直すことに反対しなかった。シュヴィントは数週間グンドラッハの家に滞在しその傷を直した。
「私」その件について忘れかけていた頃、またまたシュヴィントが血相を変えてやって来る。シュヴィントが傷を直し終えようとしたとき、背景にナイフで切ったような新たな傷が発見されたという。完全に頭に来たシュヴィントは、グンドラッハが、家を出て行ったイレネとその愛人である自分に復讐するために絵を傷つけているのであり、自分は絵を買い戻すという。シュヴィントの連れている若い女性は、グンドラッハの妻、イレネであった。
グンドラッハと話すために、壮大な屋敷に彼を訪れた「私」は、初めてその話題の絵を見る。それはドアよりも少し大きいサイズの絵で、裸で階段を降りて来るイレネが描かれていた。「私」はその絵を見て、改めてモデルのイレネに魅せられる。数日後、今度はイレネだけが「私」の事務所を訪れる。彼女は、シュヴィントには金がないので、絵は自分が買い戻すことになると言った。「私」は彼女を職場である美術館まで送る。私は完全に彼女に恋していた。そして、彼女と一緒になった後、一緒に過ごす夢を見始めていた。
グンドラッハは、「私」に奇妙な契約書の作成を依頼する。それは、
「グンドラッハが絵をシュヴィントに渡す代わりに、シュヴィントはグンドラッハにイレネを返す。」
という内容であった。その取引は日曜日の七時にグンドラッハの屋敷で行われることになった。イレネの人権を無視した人身売買のようなその契約について、「私」はイレネに忠告する。彼女は「私」に取引の行われる日、シュヴィントはワゴン車でグンドラッハの屋敷に来るだろう。そのワゴン車の中に隠れていて、シュヴィントが絵をトランクルームに積み込んだら、間髪なく発車させるようにと「私」に頼む。「私」もそれを引き受ける。
当日、私は近くの村に車を停め、グンドラッハの家の前に身を隠している。シュヴィントとイレネがワゴン車で現れ、グンドラッハの屋敷の中に入る。「私」はイレネから預かった鍵でワゴン車の運転席に乗り込み身を沈める。しばらくしてシュヴィントが絵を持って現れ、後部の扉を開け、絵を積み込む。私は車をスタートさせる。シュヴィントはもちろん追ってこられない。私は塀を乗り越えて外へ飛び出したイレネを拾う。
村の外れで、イレネはここからは独りで運転するから、私に自分の車でアパートに戻り、待っているように言う。私は、アパートに戻ってイレネを待つ。しかし、その後、イレネが戻ってくることはなかった。翌朝、私は「グンドラッハ」からイレネと絵が行方不明になっていることを知る。
二〇一〇年、シドニー
イレネと絵の事件から四十年経った。「私」は、自分の弁護士事務所を起こし、結婚し、子供をもうけた。しかし、妻を交通事故で数年前に亡くしていた。「私」は、サウス・ウェールズ美術館の館長に会って、絵を寄贈した人物の名前を教えて欲しいという。館長は守秘義務を盾に教えることに難色を示す。絵には「盗難届」等も出ておらず、合法なものであるという。
「私」は知り合いの弁護士に、探偵事務所を紹介してもらい、その絵が誰から寄贈されたものかを捜すように依頼する。数日後、その探偵事務所の所長から面会を求められる。所長は、その絵を寄贈したのはイレネ・アドラーという人物であることを告げる。彼女は二十年前に観光ビザでオーストラリアに入国し、その後非合法で国に留まっているという。彼女はドイツの銀行のクレジットカードを使って支払いをしており、ロック・ハーバーという海辺に住んでいるということであった。そこはシドニーから少し離れた場所だった。
「私」はレンタカーでロック・ハーバーへ向かう。村に着いてそこの住人に尋ねると「アイリーン」はそこから少し離れた海岸に住んでいるが、そこへはボートでしか行くことはできないという。彼女は二週間に一度くらいの間隔で、ボートに乗り村に買い物に来るという。私は、その住人の息子にボートで「アイリーン」の住む海岸まで送ってもらう。海岸には二軒の家があった。二軒とも窓は開いていたが中に誰もいなかった。私はその一軒の家で眠ってしまう。
私が目を覚ますと隣にイレネが横に座っていた。四十年ぶりの再会であった。
「わたしの勇敢な騎士。」
と言った。その低い声は四十年前と変わっていなかった。彼女はこの場所で、看護婦として病気の住人を助ける傍ら、畑を耕し、動物を飼いながら生きていた。また、社会に馴染めない子供たちを引き取っては、一緒に暮らしているということであった。夕方には村へ戻る予定にしていた「私」だが、その夜はイレネの家に泊まることにする。私が作った夕食をふたりで食べた後、イレネは二階の寝室に向かおうとするが、彼女は衰弱しており、ひとりでは階段を昇れない状態であった。「私」は彼女に手を貸す。
翌朝、ふたりはジープで、彼女が持つ農園へ行く。ヘリコプターが島の上空に現れる。着陸し、そこから現れたのはペーター・グンドラッハであった。彼も、シドニーの美術館に「階段の上の女」があることを知り、その寄贈者を調べ上げてやってきたのだった。グンドラッハは、
「シュヴィントがあんたをここへ送ったのかい。」
と尋ねるが、「私」は否定する。事業で成功を収めたグンドラッハであるが、足が悪く杖をついていた。グンドラッハとヘリコプターのパイロットをその夜は四人で過ごす。
翌朝、ボートでシュヴィントが到着する。彼は、美術館と交渉し、絵をニューヨークへ貸し出すことに同意を得てきたという。シュヴィントは、イレネに一緒にニューヨークへ行こうと誘う。グンドラッハとシュヴィントの間に、絵の所有権をめぐる口論が起こる。イレネは、
「絵は、私が美術館に寄贈したものであり、今は美術館に所有権がある。」
と明言する。イレネが絵を持ち去った後、グンドラッハは盗難届を出していなかった。そn時点で、グンドラッハの所有権は失効しているというのであった。「私」が次に家に戻ると、グンドラッハとシュヴィンツは和解しているようであった。その夜は、皆で夕食を取ることになり、私とグンドラッハは、ヘリコプターでシドニーまで食材を買いに行く。そして、その日の夕方、晩餐がはじまる。黒い服を着たイレネが階段を降りて来る。その姿は「私」にとって、四十年前と変わらない美しいものでああった。
イレネは、三人の男と別れてから自分が何をしていたかを話す。彼女は東ドイツに渡り、そこで祖母の遺産で暮らしていた。当時の東ドイツは、一切けばけばしいものがなく、彼女が心を癒すためには絶好の場所であった。しかし、東西ドイツの統一がなされ、西側の文化が東側に濁流のように流れ込み、東ドイツそのものが消滅してしまった。東ドイツのパスポートが切れる直前の一九九〇年に、イレネはオーストラリアを訪れ、その後はパスポートもなく非合法な移民として住んでいるという。幸い、祖母の残した遺産があり、支払いはドイツで発行されたクレジットカードで行われているという。
しかし、グンドラッハはイレネが東ドイツに住むようになった本当の理由を知っていた。テロリストとして、指名手配されている女性のポスターが、かつてあちこちに貼られていた。帽子をかぶり、サングラスをしているものの、それは紛れもなくイレネであった。彼女は西ドイツでは、殺人の容疑者として指名手配中であったのだ。
翌朝、シュヴィントとグンドラッハはヘリコプターで去る。「私」も一緒に来ないかと誘われるが、「私」は残ることにする。なかなか起きてこないイレネを心配した私がイレネの寝室を訪れると、イレネは吐瀉物と排泄物の悪臭の中で横たわっていた。彼女はもう身体を起すことができないという。私は彼女を浴槽に運び彼女の身体を洗い、汚れた寝具や衣服を洗濯する。イレネが再び清潔なベッドで横たわったとき、彼女は自分が膵臓癌であり、数週間の命であることを「私」に告げる。
イレネはベッドの横に座る「私」に話をしてほしいという。それは、
「もし自分がグンドラッハから絵を奪った後、『私』のアパートを訪れていたらどうなっていたか。」
という作り話であった。「私」は元々、子供たちに作り話をするのが好きであった。「私」は自分の想像のなかで、ふたりがどのような暮らしをしていたかの話を始める。それは一日では終わらず、日々続くものであった。イレネは日に日に衰弱していった。「私」はイレネを献身的に介護した。
ある日、煙の臭いに気付いた「私」は、近くに住む青年と一緒に丘へ上がってみた。山火事であった。そして、その山火事は着実にイレネの住む家の方向へと向かっていた・・・
<感想など>
主人公の「私」は、六十代のドイツ人弁護士である。シュリンクの書き方は徹底していて、この主人公の名前は一切登場しない。私(筆者)はまず、
「またか。」
と思った。シュリンクの主人公は、彼自身と同世代の法律関係の職業を持った男性が多いのである。もちろん、シュリンク自身が法律家で、その主人公と考え方、立場を最も強く共有できるという利点はあるが、もう少し冒険して、たまには作者とは全く別の年齢、性別、職業の人物を主人公にしてほしいと思う。
主人公は二十代の半ば、フランクフルトで弁護士として働き出したころ、ひとりの女性に恋をする。そしてその女性との生活を夢見る。結局その女性は忽然と姿を消してしまい、四十数年後、オーストラリアの人里離れた海岸で彼女と再会する。彼女は癌に侵され、数日から数週間の命であった。主人公は彼女の最後の日々を一緒に過ごすことになる。人生も残り少なくなったころ、かつて好きだった人に再会してみたいという気持ちは良く分かる。そして、その再会が叶うひとは幸運だ。そして、その再会の舞台が、予期せぬものであればあるほど、再会はドラマチックなものとなる。その点、オーストラリア、四十年後、癌で死ぬ運命にある相手、それを演出する舞台は整っている。ちょっと整い過ぎているくらい。このうちひとつくらい欠けても、まだ劇的であって、もう少し現実味が増すと思うだが。同時に、イレネの数奇に満ちた経歴、グンドラッハとシュヴィントのイレネを巡る争いが、ストーリーラインとなっている。
「階段を降りる女」の絵は存在する。これまで実在する絵をテーマにした小説は多い。この物語も御多分に漏れない。その絵を描いた画家はゲルハルト・リヒター。現代のドイツを代表する画家とのことである。シュリンクはその絵にインスピレーションを得てこの小説を書いたとのことで、「絵」のみが実在し、それにまつわるエピソードや人間関係は全てフィクションである。絵についての描写が小説の中に数多く出て来る。そして、それは実際の絵を見るとなるほどと納得がいくものである。ただ、ひとつだけゲルハルト・リヒターと登場人物カール・シュヴィントの共通点がある。それは、若いころ写実的な絵をかき、後年抽象画に移り、そこで成功を収めたという点である。リヒターの抽象画、一枚何億もの値がついているらしいが、私には理解を超えた芸術である。
比較的社会的なテーマを扱う作家が、二十世紀後半を舞台にして書いた小説のこれも御多分に漏れず、東西ドイツの存在、「ドイツ赤軍」によるテロ事件、東西ドイツの統一等の出来事が物語の中に登場する。イレネは、テロ事件に関与し、殺人犯として西ドイツで指名手配を受け、東ドイツに潜伏していたという設定。(当時ドイツ赤軍のメンバーは東ドイツの協力を得ていた。)そして、東ドイツの崩壊とともにオーストラリアに移り、非合法にそこに住み続けていたことになっている。シュリンクは、二〇〇八年に発表された「週末」でも、ドイツ赤軍の活動家を主人公にしている。
結論として、主人公の設定、複数のストーリーラインの組み合わせ、ドイツ政治問題の折り込み、これらのシュリンクの「常套手段」が鼻につかなければ、この物語は楽しめる。とくに、最後の三分の一、「もし自分たちが一緒になっていたら」という前提で、「私」の語る空想物語は胸を打つものがある。
(2017年5月)