「夏の嘘」
Sommerlügen
2010年
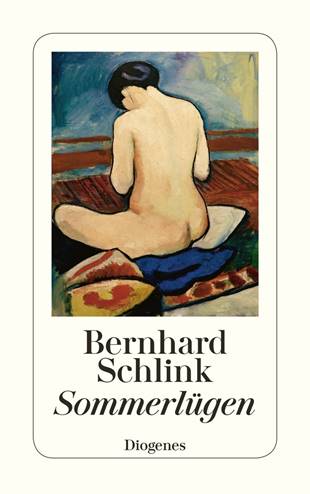
<はじめに>
ベルンハルト・シュリンクの珍しい短編集。タイトルから分かるが、共通したテーマは「嘘」。人間はどんなとき、何故、誰にどんな嘘をつくのか、その分析が面白い。
<ストーリー/感想など>
「シーズンオフ」
Nachsaison

リチャードは小さな空港で、飛行機に乗り、去っていくスーザンを見ている。彼の飛行機は一時間後。新聞とコーヒーを買うが、読む気にも飲む気にもなれない。
「独りでいることを忘れてしまったのかも。」
と彼は考える。
二週間前に、リチャードはケープに到着した。シーズンが終わり、休暇の客は去り、天気も雨ばかりだった。彼は雨の中を散歩しているとき、ひとりの女性に出会う。その夜、「魚料理の店」に独りで座っている同じ女性を見つける。独りのようである。
「一緒に座っていいですか。」
彼女はオーケーし、ふたりは食事をしながら話をする。リチャードは、自分はニューヨークのオーケストラでフルートを吹いていて、指の怪我の治療とリハビリのために、ここへ来ているという。実際、余り金のない彼は、シーズンオフにしか休暇を取れなかったのだ。ここへは両親と何度も休暇に来ているというスーザンは、普段はロサンゼルスで、貧しい子供たちが舞台に立つ機会を与える財団で働いているという。リチャードはスーザンを彼女の家まで送り、別れ際ふたりはキスをする。スーザンは、翌日のリチャードを朝食に誘う。
翌朝、リチャードは宿で目覚める。外は雨が降っている。彼は、今日スーザンと朝食を食べた後、どうなるのかと考える。散歩?サイクリング?夕食?その後は、セックス?彼は最近女性と寝たことがなく、余り女性に対して自信がなかった。彼は、宿の老夫婦が作ってくれた朝食を食べた後、スーザンを訪れる。彼女は、大きな屋敷の入り口にある、門番の家に住んでいた。彼女は、リチャードに朝食を用意していた。朝食の後、リチャードは、実は二度目の朝食であることを白状し、腹ごなしに運動がしたいと言う。スーザンは、泳ぎに行こうと言う。彼女は、タオルとシャンペンを持ち、屋敷の中を通って、プライベートビーチに向かう。
円柱が立ち並ぶ屋敷を通ってふたりは海岸に出る。スーザンは全裸になって海に飛び込み、リチャードもそれに続く。リチャードは途中でスーザンを見失いパニックになる。彼女は先に、岸に上がっていた。何故、自分の横を通って帰らなかったのかとリチャードは怒って尋ねる。
「私、極度の近視なのよ。あなたがどこにいるか見えなかったの。」
とスーザンは言う。二人は海岸の木の下に座って、雨を避けながらシャンペンを飲む。
「あなたの生い立ちと家族、全てを話して。」
とスーザンはリチャードに言う。ベルリン出身の彼は、息子を音楽家にしたいという両親の希望に従い、音楽学校に通い、今ではニューヨークフィルの第二フルート奏者をやっていると話す。スーザンは、十二歳のときに交通事故で両親を亡くし、伯父母の家で育ったという。スーザンはリチャードのようなヨーロッパ人は、皆「古い世界」に属し、悲観的だと言う。リチャードはそれを否定する。雨が強くなり、二人はスーザンの家に戻る。そこで濡れた服を乾かしながら、二人はソファに座り、雑誌や本を読んで午後を過ごす。時々目が合った二人は微笑み合う。
宿に帰ったリチャードは、スーザン・ハートマンが、大きな屋敷を両親から相続し、それらを全て所有していることを知る。貧しい環境で育ったリチャードは、金持ちが嫌いだった。特に遺産相続で裕福になった人間は大嫌い。また、そのことを自分に言わなかったスーザンに腹を立てていた。彼は、スーザンを翌日訪れないでおくこと、彼女に別れを言うことを考える。しかし一緒に過ごした午後のことを考えるとその決心も付かなかった。眠れないリチャードは、翌日の早朝海岸へ行く。そこにスーザンが居た。
「早く来て!」
スーザンはリチャードを家に連れ帰る。そして、彼をセックスに誘う。
リチャードはスーザンを愛していることに気付く。背の低い、目の小さい、少年のような体つきのスーザンは、これまでリチャードが興味を持つ女性のタイプではなかった。
「最初レストランで会ったとき、あなたに笑いかけてよかったわ。あなたは躊躇しないで、すぐ私の方へ来ればよかったのに。」
とスーザンは笑いながら言う。
二人は夕方までベッドにいて、それからスーザンの車でスーパーへ買い物に出掛けた。彼女は古いがよく整備されたBMWを持っていた。執事のクラークが、彼女の留守中、建物や車を管理しているという。屋敷は客が来た時だけ使い、彼女が独りのときは、門番の家に住んでいるという。買い物の帰り、スーザンは、
「屋敷の方に移りましょう。」
と提案する。
翌日、リチャードは、スーザンの過去について多くを知る。彼女は父の死の後、複数の会社を受け継ぎ、それを売却。その資産で暮らしていた。離婚歴があり、前夫のロバートと子供を作ろうとしたが、結局できなかったという。四十一歳、リチャードより二歳上であった。今ロサンゼルスに住んでいるが、近くニューヨークに引越しする予定でいた。彼女はニューヨークにコンドミニアムを持っており、それを改装することにしているという。彼女は、自分の計画について話すとき、リチャードが自分と一緒にいることを前提にしているようであった。彼女はリチャードに、ニューヨークの住いに改装に立ち会ってくれと頼む。彼女は子供が欲しいと言う。しかし、リチャードには、自分の言葉に余り束縛されるなとも言う。リチャードは、楽譜とフルートをスーザンの家に持ってきて、フルートの練習を始める。そして、スーザンのために時には即興演奏もした。
天気が悪く海岸を散歩できないとき、二人はお気に入りの角の部屋で時を過ごした。そこには一人掛けのソファしかなかった。リチャードが残念がると、二日後、同じ模様の二人掛けのソファが配達された。天気は、ずっと良くなかった。洗濯や掃除は、執事の妻であるミタがやっていた。リチャードと、彼女にほとんど顔を合わせることがなかった。二人は一度、リチャードの元宿の主人であるジョンとリンダを食事に招待した。しかし、それ以外は、ふたりきりで過ごした。夕方になるとふたりはセックスをした。
ふたりは一度大ゲンカをした。スーパーマーケットに買い出しに行こうとしたとき、
「ちょっと電話を架けるから。」
と言って突然スーザンが離れていき、彼を三十分以上待たせたからだ。彼女が戻ってきた時、リチャードは文句を言う。
「数分間待たせただけじゃないの。そもそもあなたたちヨーロッパ人は女性に対して・・・」
と言いかけるスーザンをリチャードが遮る。ふたりは口論をしながら車で家に戻る。家に戻ったスーザンは、床に来ている物を脱ぎ捨てる。そして、リチャードを床に押し倒す。二人は床でセックスをする。その後、ふたりはスーパーへ行き買い物をする。車の中で、スーザンは謝り、泣き出す。
いよいよ最後の日になった。ふたりは夕方の飛行機で発つことになっていた。ニューヨークのコンドは、二人で仕上げることになっていたが、リチャードの貯金は、休暇の費用と、休暇中の高価な食料品の買い物で底をついていた。二人は別れることを恐れていた。スーザンは、リチャードに一緒にロサンゼルスに来ないかと誘うが、彼にはオーケストラのリハーサルがあることを理由に断る。二人はスーザンの車で空港に向かう。リチャードは、夜、ニューヨークに到着する。彼は自分の住む街に戻る。そこは、常に少年たちが通りでたむろしている下町だった・・・
休暇で出会った男女が、休暇のあと元の場所に戻る。それまでの現実に引き戻されたとき、その休暇の間に燃え上がったものを持続できるのかという、比較的、古典的な題材を扱っている。また、金のない男が、裕福な女性と知り合ってしまい、その結果、自分が金持ちに抱く劣等感や憎悪をどのように処理していくかも、テーマになっている。これも結構古典的なものと言えよう。シュリンクの作品には、彼と同じような経歴を持った人間が登場する。主人公のリチャードも、ベルリン出身のドイツ人である。新しく恋人となったスーザンは、リチャードを典型的なヨーロッパ人であると言い、「悲観的だ」、「運命論者」だと評する。この辺り、「楽観的な」、「自分の運命は変えられると思っている」米国人の気質との対比が面白い。
シュリンクは、今やドイツ純文学界の大御所、久しぶりの短編集である。この人の文章、昔から読み易いが、この本でまた一段と読み易くなっている。平易な表現、短い文、スッと頭に入って行く。年齢、経験を重ねるごとに、難解になっていく人が多い中で、シュリンクは逆を行っている。
「バーデンバーデンの夜」
Die Nacht in Baden-Baden

彼の最初の作品がバーデンバーデンで舞台にかけられることになった。その初日に彼は招待されていた。幕が下りた後、彼は舞台に上がり、喝采を受けるか、ブーイングを受けることになっていた。普段はフランクフルトに住む彼は、車でバーデンバーデンに向かう。彼はテレーゼを連れて行った。彼はバーデンバーデンでも最高級の「ブレナーズ・パーク・ホテル」に部屋を取っていた。午後にホテルに着いた二人は、風呂に入り、その後劇場に出掛ける。彼らは、演出家や俳優たちと挨拶をする。劇は、書いた本人が想像していたよりもグロテスクに仕上がっていた。しかし、観客の反応は良く、彼は舞台に呼び出され喝采を浴びた。ホテルに戻った二人は、シャンパンで劇の成功を祝う。そして、ベッドに入るが、背中を向けたまま、朝まで二人は眠る。翌日二人は、バーデンバーデンの美術館を訪れた後、町を去る。途中、ハイデルベルクの城に立ち寄って、二人はフランクフルトで別れる。
フランクフルトに戻った彼は、携帯のスイッチを入れ着信履歴を見る。恋人のアンネからは、メッセージも不在着信もなかった。彼は、今オックスフォードに居るアンネに電話をする。女性人権論の研究者であるアンネは、そのときオックスフォード大学に招待され、集中講義をしていた。彼は、
「携帯をフランクフルトに忘れていた、昨夜は遅くなり、今日は早くて連絡できなかった。」
とアンネに言い訳をする。アンネは何かがおかしいことを察していた。
「今日のあなたはどこか違うわ。」
とアンネは言う。彼は忙しかったので疲れていると更に言い訳をする。アンネは直ぐに会いたいと言う。忙しいと言い訳を始めた彼だが、結局、三日後の水曜日にオックスフォードに行くことを、約束させられてしまう。
彼は、アンネに嘘をついたこと、またテレーゼに対してもそのままになっていることに、心が痛む。彼はアンネと七年間付き合っていたが、共通の生活基盤を見つけることが出来ないでいた。彼女はアムステルダムに住み、講義を依頼されて世界各国の大学に出掛けることが多かった。彼は、アムステルダムやその他の都市にいるアンネを、ある時きは短期に、ある時は長期に渡って訪れていた。彼はアンネとは別の、自分だけの世界を持ち続けたいと思っていた。テレーゼもそのひとつだった。しかし、アンネは、彼が他の女性と関係することに極端に神経質になっていた。そして、彼の身辺について、詳しく知りたがっていた。アンネと彼は、これまで何度も大ゲンカをしていた。しかし、その都度互いへの憧れの方が強くなり、ふたりは仲直りしていた。今回、彼がテレーゼとの一夜について黙っていたのも、もうアンネとの間に波風を立てたくないためだった。
水曜日ではなく、金曜日に彼はオックスフォードを訪れる。アンネが借りているアパートに着き、彼女の仕事が一段落するのを待ち、ふたりは散歩に出かける。
「バーデンバーデンで誰と一緒にいたの?」
とアンネが突然訪ねる。
「バーデンバーデンのあちこちのホテルに電話をして、『ブレナーズ・パーク・ホテル』であなたの名前を見つけたの。つないでくれと頼んだけど、遅いからと言って断られたわ。どうしてそのホテルに泊まるって前もって言わなかったの?」
彼は、
「随分前に予約したんで、忘れていたんだ。」
と答える。
「あそこは一泊四百ユーロよ。どうしてそんな高いホテルに泊まったの?」
とアンネは更に尋ねる。
「前から憧れていて、一度泊まりたいと思っていたんだ。」
と彼は答える。
「そんな憧れのホテルに泊まることを忘れていたの?どうして嘘をつくのよ!」
答えに窮した彼は、
「とにかく初演の前は忙しく、色々なことを考えて、覚えている余裕がなかったんだ。」
と、言い逃れる。
夜彼が目を覚ますと、ベッドの中でアンネが泣いている。彼はアンネを抱き寄せる。
「私は嘘の中で生きたくない。父親は母親や私たちにいつも嘘をついていたわ。子供の頃、私にはしっかりした地面がなかったの。私は、生きていくための、確固とした地面が欲しいのよ。」
彼は一瞬テレーゼとの夜のことをアンネに話そうかと考える。しかし、
「今話してどうなるもんでもない。これから嘘をつかないようにしよう。」
と思い、そのままにすることにする。
三週間後、ふたりはプロヴァンス地方で、安い部屋を借りて休暇を過ごす。厳密にいうと、それは休暇ではなく、彼は新作を、アンネは論文を書くための時間だった。しかし、間もなく彼らは執筆に興味を失い、カフェや屋外で時間を過ごすようになる。家にインターネットがなかったので、二人は頻繁に図書館に行き、メールをチェックする。ある日、アンネは
「子供が欲しいの。」
と言う。彼はアンネに、結婚して、フランクフルで一緒に住むことを提案するが、アンネは、職業上の空白期間に、自分が世間から忘れられるのではないかと心配する。
「本当に優秀な人間を、世間はそう簡単に忘れない。変わっていく世界に対して、順応していくことも大切だ。」
と彼は言う。その夜、彼はアンネにプロポーズをする。アンネは考えさせてくれと言うが、ふたりはともかく「プロポーズ」を記念してシャンパンで乾杯する。
数日後、昼間セックスをした後、アンネは図書館へメールをチェックしてくると言って出て行く。彼女は夕方になっても帰って来ない。午後九時になり、心配になった彼は街へ出る。あるバーで、アンネは煙草を吸っていた。
「あんたのメールを見たわ。テレーゼと一緒にホテル泊まったのね。」
「お前は、俺のメールを盗み読みしたのか。何の権利があって!」
「あんたは、大嘘つきの糞野郎だわ。嘘をつくしか能のない無能者よ!」
アンネは人前にも関わらず、大声で彼を罵る。
「俺にも言わせてくれ。テレーゼとは寝てないんだ。」
「被害者ぶるのはよして。自分が言ったこと、やったことに責任を持ちなさいよ。あんたの言うことなんて信じられないわ。」
そう叫んでアンネは立ち去る。彼は、アンネを追おうとするが思い止まる。彼は車に乗り、山に向かって車を走らせる・・・
この物語には、ふたつの大きな教訓がある。
ひとつは、嘘はついちゃいけないということ。ついてしまったら、出来るだけ早くそれを認めて本当のことを言う。そうしないと、嘘を隠すためにまた別の嘘をついて、遂には身動きが取れなくなる。二つ目は、決心したことは、その瞬間から守らなければいけないということ。「次から」、「明日から」と思うと絶対にできない。
この主人公「彼」と呼ばれるだけで、名前は出て来ない。フランクフルトに住む、若手の劇作家である。ともかく、彼は、一晩を彼なりの事情で、テレーザという女性と過ごす。ふたりはセックスをしていない。そして、それをガールフレンドのアンネに言わないでおく。研究者であるアンネは、詮索好きの女性である。彼の行動を徹底的にリサーチ、クロスチェックする。アンネは自分の知り得た事実を基に彼に迫るが、彼は新たな嘘を繰り出してそれを避け、結局より深い墓穴を掘ることになる。ただ、アンネの執拗なリサーチが、最後にこのストーリーの結末と密接に関連している。それが面白い。
彼は、一度はアンネの説得に動かされ、彼女には嘘をつかないでおこうと決心する。しかし、彼は「次から」、「今度から」と考えてしまい、それまでの嘘については押し通すことにする。その結果、先にも書いたが、まずい結果を生んでしまう。
人間は理路整然と動く存在であると思う。理屈の通らない行動は、嘘であるか、別の理屈があるからなのだ。
「忙しかったから、混乱していたから、自分でも分からない行動を取ってしまった。」
と言うのは、自分の嘘を認めているようなものである。
私事になるが、私はこれまで嘘をつかれたこともあるし、嘘をついたこともある。嘘をつかれていたことが分かるのは、大きなショックである。そういう意味では、アンネの気持ちも良く分かるし、彼女の取った徹底したリサーチ、クロスチェックという手法も理解できる。しかし、「疑ってだまされない」のと「信じてだまされる」のと、どちらが楽かという点は別問題であると思う。アンネは前者である。私自身は後者であると思う。
「森の中の家」
Das Haus im
Wald

彼はこの森の中の家に、ずっと妻と娘と住んでいるような錯覚を覚えることがあった。週に一度、彼は妻のケイトと娘のリタに見送られ、近くの町に用足しと買い物に出掛ける。車に乗ると気分が悪くなる妻と娘は付いて来ずに、玄関で彼を見送った。数時間後、彼が用事を済ませて帰って来ると、二人は車に駆け寄り、荷物を降ろすのを手伝った。彼らは三人きりで人里離れた家で暮らしていた。週に一度程度、ケイトは家族と時間を過ごしたが、それ以外の時間、彼女は執筆をしていた。その間、時には一日中、彼は家事、庭仕事をし、娘の相手をしていることもあった。しかし、彼はそのような生活をアクセプトし、楽しんでいた。彼は、このような生活がずっと続くことを望んでいた。
ニューヨークで暮らしていた彼らは、半年前にこの田舎の家に越して来ていた。ケイトが都会の喧騒や雑用から逃れて、執筆活動に集中したいというのが、その理由だった。しかし、ケイトはニューヨークから余り離れ過ぎるのも望まなかった。ニューヨークから車で五時間の、この場所に家を見つけたのが秋、ケイトも気に入り、ふたりは草原と森に囲まれた家を買った。冬の間家の改装をし、春に越してきたのであった。ケイトはそこですぐに執筆を始めた。ケイトも彼も作家ではあったが、ケイトが登り坂であるのに対し、彼は一作目がヒットしてから次の出版の話はなかった。彼はドイツ人、ドイツでベストセラーとなった自分の処女作の英語訳の出版で米国に来た。そのとき、パーティーでケイトと知り合ったのだった。いつの間にか、彼は専業主夫の立場を務めるようになっていた。ケイトの父はハーバード大学の教授で、母親はコンサートピアニストだった。幼い時から養育係の女性に、効果的に育てられていた。そのせいか、彼女は余り自分の娘にも興味は持たず、「子供は勝手に育っていく」と考えているようなところがあった。それに対し、余り裕福でも幸福でもない家庭に育った彼は、自分の憧れていた家庭と子供は、何よりも大切で、生き甲斐だった。彼は、両親が喧嘩を始めると、自分の立っている足元の氷が割れるような気がした。自分とケイトは、厚いしっかりした氷の上に立っていたいと思っていた。彼らが最初に出会ったとき、彼は新進気鋭の作家で、自信満々だった。その自信に満ちた態度がケイトの気に入ったのか、二人は恋に落ち、半年後に結婚した。その後、ケイトはベストセラーを連発し、外出が多くなり、疲れ始めていた。子供が出来たとき、ケイトは、子供と執筆だけの生活に憧れる。そんな生活を実現するために、彼らはニューヨークを離れて、田舎に移り住んだのだった。
季節は秋になり、リンゴが色づいてくる。ケイトは執筆に余念がない。それは彼女の四冊目の本だった。ケイトは、夫に執筆中の作品を読んで欲しいという。彼女は完成するまで作品を誰にも見せないのが普通だった。彼は信頼されていると喜ぶ。彼女の前の三作はベトナム戦争から帰って来た元兵士の話だった。四作目は、海外から養子縁組をしようとしているカップルの話だった。養子縁組は上手く行かないが、カップルは別の新しい生活を始めることにする。彼は原稿を読んで、
「これは自分への警告ではないか?」
と考え始める。新しい生活を始めたいというケイトの願望が現れているのではと、勘ぐったのだった。彼は改めて、自分と妻の間に問題はないのかと考える。
「問題はないはずだ。」
彼は、自分にそう言い聞かせる。
その週も、彼は町へと車を走らせる。彼は、ケイトが候補者に挙がっている文学賞の発表が近づいていることを知っていた。そろそろ初雪が降る季節だった。スーパーの主人は、彼に、一八七六年の冬について話をする。初雪が降り始めた後、何日も激しい降雪が続き、春まで、この一帯は雪に降りこめられ、孤立したという。そして、周囲との行き来を絶たれた家の人々が、沢山凍死、餓死したという。
「大雪が降って孤立したら、ケイトはどこにも行かなくて済み、自分たちは誰にも煩わせられない。」
彼はそんなことを考える。彼が本道を離れ私道に入ると、彼らの家のために張られた電話線の傍に、大きな枯れ木が立っていた。彼はその枯れ木にロープを掛け、車で引っ張り倒してしまう。倒れる際、木は電話線を切断していた。彼は、達成感と罪悪感の両方を持ち、家に戻る。
ケイトは、インターネットと電話が通じないことに気付く。数日後、彼女は夫に、町へ行って技術者に修理を依頼してくれるように頼む。ふたりの住む辺りには、携帯電話のアンテナもなく、ケイトは外界との接触を一切絶たれたのであった。ベッドの中でケイトは、
「セックスはニューヨークでする方が良い。」
と言う。
「ここでのセックスは、リタイアした老夫婦のセックスみたいで、刺激がない。」
と彼女は続ける。彼は、妻が、今の本を書き終わったら、ニューヨークに戻るのではないかと真剣に心配しはじめる。そして、その本の完成の日は、近づいているようであった。
翌日、彼は町に行く途中、電話線をチェックする。切断されたままであった。電話会社に言っても、怪しまれることはないだろうと彼は確信する。しかし、電話会社に言わないというのも一つの選択であると彼は考える。そして、町の電話技師は今日も不在だった。彼はスーパーで、ニューヨークタイムズを見る。一面の記事に、ケイトが今年の文学賞を受賞したことが載っていた。彼はその新聞を買う。
「本人は現れないで、代理人が賞を受け取った。」
と記事は伝えていた。
季節は冬に向かっていた。彼は三人だけで過ごす冬を楽しみにしていた。親しい友人なら呼んでもいいと彼が考えたとき、彼はある事実に気付く。四人の友人たちが、彼らの今の住所を知っているのである。ケイトが文学賞を受賞した今、一両日中に友人たちが祝福に現れるのは、十分考えられることであった。家に帰った彼は、ケイトに技術者の不在を伝える。ケイトは田舎のインフラの不整備をなじる。そして、携帯が使えるように、裏山にアンテナを建てようと言い出す。
彼は深夜、外へ出る。音がしないように車を家から離れたところまで押し、そこから町へ向かう。彼は警察署の駐車場の前にあった、「進入禁止・警察」と書いた横木と支柱を盗む。そして、その車止めを本道から、彼の家の前に続く私道への入り口に設置する。
少しヒヤヒヤしていた彼だが、友人たちも、警察官も、彼の家を訪れることはなかった。そんなある日、ケイトが言う。
「新しい本は殆ど終わったわ。これまで、辛抱強く待っていてくれて有難う。これで、私たちの生活は変わるわ。ついては、お客さんを招待したいんだけど。」
彼はショックを受ける。ケイトは更に、
「明日、町のインターネットカフェへ行って、メールをチェックして来るわ。」
彼は狼狽する。彼は、ケイトが外界と接触するのを、何としても阻止せねばならないと思う。
日曜日にケイトは最終的に脱稿する。彼女は、娘のリタと上機嫌で料理を作り始める。彼は独り残されたような気分になる。
「明日、町へ出るので車を使うわよ。」
とケイトは言う。
「明日は、友人と屋根の修理をするので車が居る。それに、リタを独りで家に置いておくわけにはいかない。」
と彼は反論する。
「大丈夫、リタは一緒に連れて行くわ。町で降ろしてくれて、後で拾ってくれたそれでいいから。」
とケイトは言う。彼は、リタが車に酔うから可哀そうだと言う。どうしても町へ行くと言うケイトと彼は口論になる。
翌朝、彼が目を覚ますと隣にケイトがいない。窓の外を見ると、ケイトがリタを連れて車に乗り込もうとしていた。
「やめろ!」
彼は家から走り出し、車に手を掛けて停めようとする。ケイトは強引に車をスタートさせる。車が見えなくなる。その直後、衝突音が聞こえる。ケイトの運転する車が、彼の置いた車止めにぶつかったのだった・・・
このストーリーを読んで、私はウーヴェ・ティムの小説「カレーソーセージの発明」を思い出した。作品はベストセラーになり、映画化もされた。第二次世界大戦末期、未亡人のレーナは、休暇でハンブルクに来ていた兵士ブレーマーと出会う。彼女は、ブレーマーを自分のアパートに連れ帰る。彼を戦場に返したくないレーナは、彼を一室に閉じ込める。そして、ドイツ軍が反撃に転じ、戦闘に勝ち続けているとブレーマーに説明する。実際に、その間にドイツは敗戦を迎える。今更引けなくなったレーナは、彼に次々と色々な嘘をつく。そんな話だった。
「森の中の家」の主人公も、名前が分からない。「彼」としか書かれていない。ドイツ人である。そして、相手の女性は非ドイツ人。この短編集のそれまでの二つの作品のパターンを踏襲している。幼い頃、幸福でない家庭生活を過ごした彼は、幸福な家庭生活に憧れる。そして、田舎の森の中に買った新しい家で、ベストセラー作家である妻と、幼い娘と一緒に住み始める。それは彼のかけがえのない幸福であった。彼は、何としてもそれを守ろうとする。自分たちの生活を、外界から断ち切ることによって。その辺りから、彼の考え方はだんだんと病的になってくる。最初の嘘の隠すために次の嘘をつき、嘘は雪だるま式に大きくなる。そしてそれが崩れるときが来る。
最後に、彼の妻のケイトは、
「あんたは気が狂っているわ!」
と叫ぶが、その通り、彼の行動は明らかに異常である。しかし、最初は単に幸せな家庭に憧れる「普通の人間」が、だんだんと、病的な異常行動を示すようになるその過程が興味深い。正気と狂気は紙一重、人間は簡単にその境を超えてしまう、そんなことを考えさせられる作品であった。
「夜の見知らぬ男」
Der Fremde in der Nacht

私はニューヨークの空港で、フランクフルト行きの飛行機を待っていた。飛行機は悪天候のため、遅れて出発した。ファーストクラスに座っている私の隣に、中年の男が座ってきた。食事が終わり、機内が暗くなる。隣の男性が私に、彼の奇妙な体験を話し始める。
「私は、湾岸戦争の頃、ドイツ内務省のあるポストに就いていた。ある日、外務省の主催したパーティーに、ガールフレンドと一緒に出掛けた私は、クウェートの外交官と知り合う。そのクウェートの外交官は、私のガールフレンドを、美しい、素晴らしい、天使のようだと褒めちぎる。
そのパーティーの後、私とガールフレンドは、その外交官に招待され、クウェートを訪れる。その外交官が毎日接待をしてくれ、私は『お大尽』気分を味わった。ある朝、ホテルの入り口で、私とガールフレンドはタクシーに乗ろうとした。その時、二人の男が乗った黒塗りの車が現れ、私たちを迎えに来たと言った。私たちはその車に乗ってしまった。信号で車が停まったとき、運転手が手紙を私に渡し、道路脇のポストに入れてくれと言う。手紙を受け取って、車を降りたとたん、車は走り出し、見えなくなった。私は、すぐに外交官に電話をし、誘拐事件として警察が捜査をしたが、結局ガールフレンドは見つからず、私は独りでドイツに戻らざるを得なかった。家に帰った私は、女性の人身売買について知った。容姿の良いヨーロッパ人の女性は、高値で取引され、協力を拒否した女性は、アフリカの売春宿に売られるという。大抵の場合、好みの女性を選ばせて、その女性をターゲットにして誘拐するという手段が取られているとのことだった。
一年後に湾岸戦争が起こった。クウェートの金持ちは、国外に脱出を始めた。ジュネーブに脱出した家族から、私のガールフレンドは逃げ出した。彼女は、車を停めて、運転者の携帯から私に電話をしてきた。私は慌ててジュネーブに飛んで、大学の図書館に隠れていたガールフレンドに会った。彼女を誘拐したのは、例のクウェートの外交官であったのだ。彼女は、私との再会を、どこか、心から喜んでいないように感じた。私は当時それをトラウマのせいだと考えた。私たちはスイスの警察に行ったが、ドイツの警察へ行くように言われた。ドイツの警察に行くと、今度はスイスの警察に行けと言われた。湾岸戦争の直後であり、どの国も、『被害者』として保護されるべきクウェートとの間に、諍いの種を持ちたくなかったのである。」
私たちの乗った飛行機は、気流の悪い場所に差し掛かったのか、激しく揺れた。棚の荷物が落ち、嘔吐する乗客が出た。私は、上の空で男の話を聞いていた。
「・・・彼女は死んだ。」
男のその言葉で、私は我に帰る。
「私と言い争っている間に、彼女は三階のバルコニーから落ちて死んだ。彼女が殴ってきたので、私は彼女を押し返しただけ。あれは事故なんだ。」
と男は言う。
「金の問題があるので、マスコミが飛びついてきた。実は、ガールフレンドが行方不明になったとき、私の口座に三百万ドルの振り込みがあった。現金での振り込みで、誰かは分からない。しかし、私はクウェートの外交官からのものであることを疑わなかった。一度外交官は、『ベドウィンラクダと女を交換する。いくらなら彼女を譲ってくれる?』と聞いてきたことがあった。私は冗談だと思って、『ラクダ百匹となら』と答えた。金が振り込まれたとき、私は単なるゲームだと思った。しかし、ガールフレンドはその金に気付き、私が本当に彼女を売ったと思い込んだ。それが言い争いの原因だった。ところが、彼女は女友達に、その金の存在を話しており、彼女が死んだ後、私が殺したのではないかと警察に訴えたんだ。」
機内にアナウンスがあった。乱気流で、機体に損傷が起こった可能性があるため、アイスランドのレイキャビクに緊急着陸し、機体のチェックを行うとのことであった。男はドづける。
「警察には証拠がなかった。しかし、私には不利な点がふたつあった。私は三百万ドルを運用し、かなりの利益を得ていたこと。また、隣人の女性が、私とガールフレンドが言い争っているとき、私が彼女を押したと証言していることであった。それを、知った時、私は、金をタックスヘイブンの国の口座に移し、ドイツを去った。ドイツの警察は今でも私を探している。言い忘れたが、ガールフレンドはアヴァという名前だ。美しい女性で、私は彼女と一緒にいるところを、他人に見られるのが好きだった。しかし、それは虚栄ではない、愛だ。」
飛行機はレイキャビクに着陸する。私と隣人はラウンジで出発を待つ。
「あの窓際にいる白いスーツを着た男に私は追われている。」
と男は言う、
「私はドイツを出た後、しばらく南アフリカのケープタウンの海辺に住んでいた。ある日、匿名の手紙が届いた。その中にはストーリーが書かれていた。『族長の下から一人の女性が逃げ出した。その女性はお気に入りだったが彼はそれを許した。数年後、その女性の新しい夫がその女性を殺した。族長はためらわずその男を殺した。自分の所有物が自分の道を行くことは許せるが、自分の所有物が壊されるのは許せなかった。』その手紙を受け取った後、家の前に、あの白いスーツの男が現れた。」
男は続ける。
「あの白いスーツの男は、私をずっと尾行し、ある日、私を撃った。私は軽傷で、病院に運ばれたが、すぐに海外に逃げることを決意した。次に住んだ場所はカリフォルニアの海辺だった。そこで、私はイラストレーターのデビーという女性と知り合い、一年間楽しく暮らした。しかし、一年後に、白いスーツの男が再び私の前に現れた。私はドイツに戻り、裁判を受けることにした。クウェートの外交官のヒットマンも、刑務所の中までは追って来ないと思うからだ。今フランクフルトに向かっているのはそのためだ。」
その後、男は私にとんでもないことを話す。
「パスポートを貸してくれないが。ドイツへ戻って、母親と弁護士に会ってから自首したいんだ。幸い、あなたとは年恰好が似ている。あなたのパスポートで、私は入国できると思う。あなたはパスポートを盗まれたと言えばいいんだ。」
そう言った後、男は席を立った。
私、ヤコブ・サルティンは、ダルムシュタット大学の交通学の教授をしている。私は、偶然電車の隣に座った男が、殺人を犯したと話す本を読んだことがあった。今日、隣に座っている男の言うことは本当なのだろうかと、私は考えた。ひょっとしたら、警察や弁護士の前でつく嘘を、私を相手に練習しているのではとも考える。あるいは、最初からパスポート目当てに渡しに近づいて来たのかも知れない。しかし、私がファーストクラスに乗ることになったのは、オーバーブッキングのためで、全くの偶然なのだ。世の中には、金のために何でもする人間がいるが、隣の男はそんな風には見えなかった。私は、そんなことを考えながら眠ってしまう。
代替機の到着のアナウンスがあり、私は搭乗口に向かう。飛行機はレイキャビクを飛び立つが、フランクフルトに着くまで、隣の男とは殆ど話をしなかった。フランクフルトに到着する。飛行機を降りる前、男は私を抱きしめる。そして、急いで降りていき、姿が見えなくなる。パスポートコントルールの前で私は立ちすくむ。ジャケットの内ポケットに入れていたはずのパスポートがなくなっている・・・
「私」、飛行機の中で、隣に座った男から聞いた話を語るという「枠小説」である。隣席の男の名前は分からない。「五十歳くらいの身なりの良い男」と説明され、ファーストクラスに乗っているというので、それなりに金持ちであることが暗示される。語り手の「私」の正体が分かるのは、もう終盤になってから。最初は男か女か、歳は幾つくらいかも分からないままに話が進む。はっきり言って、「私」の正体をここまで隠す必要があったのか、疑問に思う。「私」の正体が分からないがゆえに、読んでいて、光景を想像するのに苦労をした。
隣席の男の語る話は奇妙である。一九九〇年、湾岸戦争の始まる少し前、ガールフレンドとクウェートに旅行に行ったとき、ガールフレンドが何者かに誘拐されてしまう。一年後、彼女は囚われの身から逃げ出し、再び男の下に戻る。彼女を誘拐したのは、知り合いのクウェート人の外交官であった。男は外交官に、
「ラクダ百匹と交換なら、彼女をあんたに譲ってもいい。」
と冗談を言った。そして、彼女が誘拐されてから、大金が彼の口座に振り込まれた。ガールフレンドは、彼が自分を売ったと信じている。ベランダでふたりは口論になる。殴ってくる彼女を男は突き返す。彼女はバランスを失ってベランダから落ち死亡する・・・そんな話が、男の口から語られる。
さて、この短編集の共通のテーマは「嘘」である。隣席の男の語る話は、一応筋が通っている。男は「冗談で」ガールフレンドを譲ると言い、結果的に「事故で」彼女を死なせてしまった。しかし、彼が本当はガールフレンドを「売り」、口封じのために「殺した」と解釈できないことはない。語り手の「私」も、男の話したストーリーをどう解釈して良いのかと悩む。そして、「私」が下した結論とは・・・という点が物語の興味となる。
またまた主人公はドイツ人の男性で、中年の大学教授。作者シュリンクの分身とも言ええる。シュリンクは、主人公の設定について決して「冒険」しない人である。いつも、自分の生い立ち、自分の経歴と似た人物を主人公として登場させる。それが少し物足りなくもある。
「最後の夏」
Der Letzte Sommer

トマス・ヴェルマーは、初めて大学に招聘され、ニューヨークで働いたときのことを思い出していた。彼はドイツの大学で哲学を教えていた。初めてニューヨークの大学に呼ばれたとき、彼は憧れの街に住めることが嬉しかった。ニューヨークでは孤独で、生活環境も悪く、病気にもなったが、彼は自分が幸せだと思い込もうとした。彼は自分が幸せになる材料を必死で集めようとした。しかし、それで幸せが出来たかという自信はなかった。
現在、彼は湖の畔に座って、孫たちの遊んでいるのを見ていた。彼は自分の女性関係を振り返っていた。彼が最後にニューヨークで働いたとき、彼は一人の女性と、自転車がぶつかったことが縁で親しくなった。その女性としばらく一緒に暮らしたが、彼女は引越し、彼もドイツに戻り、それきりになった。彼の初恋は、十五歳のとき、バルバラという、学校のクラスで一番可愛い娘だった。次に十九歳のとき、ヘレナという年上の女性を好きになり、数年間一緒に暮らすが、彼女がロンドンへ行き、二人は別れていた。彼はその後、現在の妻と結婚し、大学を卒業、教授になれた。自分は幸せだったのだろうかと彼は考える。そして、少なくとも、今、四週間、子供たちや孫たちと一緒に過ごせる自分は、幸せだと思う。それは、彼が予想していたのと同じ展開であった。
彼は、医者と同僚が処方してくれた安楽死のための薬を持っていた。それを夜に飲むと、翌朝死んでいるところを発見され、死因は心臓麻痺ということになるはずだった。彼は孫たちとの生活を満喫していた。彼らの作り出す物音は、心地の良いものだった。妻は長年教師をしていた。彼は、妻との関係を、特に親密だとは思わないものの、長年連れ添ってきた夫婦としては普通のものだと思っていた。天気も良かった。
「この幸せの中に不幸が潜んでいるとすれば、それは何だろう。」
と彼は考える。
夜、ベッド中で、彼は妻に、
「俺と一緒に暮らしてきて、幸せだったか?」
と尋ねる。
「あなたは、何時も家を空けていたじゃない。私は、もっとあなたと一緒に居たかったわ。」
妻は答える。そのとき、彼は激しい腰の痛みを感じる。彼は、自分の骨が崩壊し始めているのを感じる。彼は、痛みが全身に広がるのを感じる。
翌朝、彼は誰よりも早く起きる。彼は台所で、料理の本を見ながらパンケーキを作り始める。彼はこれまで一度も、自分で料理をしたことがなかった。妻が起きてきて、驚いて何をしているのかと尋ねる。
「パンケーキを作っているんだ。試作品第一号を食べてみるかい?」
妻はパンケーキを一切れ口にする。
「悪くないわ。」
「じゃあ、ご褒美に、キスをしてくれ。」
妻はその言い方に、これまでにないものを感じる。孫が起きてくる。
「お祖父ちゃんがパンケーキを焼いている!」
孫たちは大騒ぎを始める。
朝食の後、彼は桟橋に椅子を出して、孫たちが遊んでいるのを見ていた。男の子が女の子を好きなのが分かる。彼は、孫たちの中に、五十年前の自分を見た。彼は、一番年長で十二歳になるアリアネを誘って外出する。
その夜、彼は妻と、バルコニーでワインを飲んでいた。
「今年の夏、あなたに何が起こったの。どうして今年の夏は違うの。これまでの夏は間違いだったの?」
尋ねる。彼は、
「大学を定年で辞めたが、生活習慣をそんなに速く切り替えられなかった。三年間かかって、やっと切り替えができ始めたんだ。」
と答える。
「あなたはこれまで私の身体に触れようとしなかったわ。それが急にどうしたの?」
妻は不思議がる。
翌日から、彼は前にもまして、食事や家事、庭仕事を手伝い、孫のために時間を割き、妻と一緒に散歩に出かけるようになった。彼の妻は一度乳がんの手術をしていた。その後、彼は妻の身体に余り触らないようになっていた。
「他に女がいたの?」
妻は尋ねる。
「そんな暇はなかった。」
彼は答える。
その夜、二人はベッドで抱き合っていた。彼は激しい痛みに襲われる。彼は浴室に入り、鎮痛剤を飲む。彼は寝室に戻って妻の寝顔を見る。妻は若作りをしているが、老いは隠せなかった。彼らは翌朝、実に久々にセックスをする。
翌日の昼、彼は友人を駅まで迎えに行く。友人は著名な弁護士で、穏やかな性格で、同僚やクライアント、それどころか検察官にまで好かれていた。彼の家族も友人を好いており、特に息子のヘルムートは友人の影響で、同じ弁護士の道を歩んでいた。
「がんの様子はどうだ。」
と、彼は友人に尋ねる。
友人も癌を病んでおり、これまで治療を繰り返していた。
「おまえこそどうだ?」
彼は自分の病気のことを、友人だけには話していた。
「骨が完全に折れるのは、もう時間の問題だ。」
彼は、薬と、自分の計画について、友人に話そうかと迷う。
「痛みに耐えられなくなったらどうするつもりだ?」
と友人は訪ねる。
「そのときは・・・夏を楽しむだけだ。」
彼は答える。
家族と友人は楽しく夜を過ごしていた。彼は痛みと戦っていた。医者へ行って、モルヒネを処方してもらうべきか、それとも例の薬を飲むべきか、彼は悩む。激しい痛みというのは、彼の想定外だった。友人の話は面白かった。仕事で出会った逸話を、家族に面白おかしく話した。彼は、自分のやってきた哲学の話で、家族を楽しませることが出来るかと考える。彼は、自分のやって来た仕事が「壮大な無駄」だったように感じる。友人はピアノを弾き始める。彼は妻を誘って、他の者の邪魔をしないで寝室へ行こうと誘う。
休暇の半分が過ぎた。子供たちはそれぞれの道を歩み、それは必ずしも彼の望む方向ではなかったが、彼はもう何も言わないでおこうと思った。彼は町の医者へ行き、モルヒネを処方してもらう。彼はそれを射ち、しばらくの間リラックスをする。
妻が部屋に入って来る。彼女は、安楽死の薬の入った瓶を彼に見せる。
「これは何?」
「痛み止めだ。」
「とぼけるのは止めて!」
妻はその薬の意味を知っていた・・・
「最後の夏」というタイトルからも分かるが、主人公がこの夏の休暇を人生最後の、特別なものと考えていることが、最初から明らかにされる。彼が末期ガンであることは、容易に想像が付き、実際、その通りなのである。彼が「安楽死」のための薬を用意していることも、最初の数ページで述べられる。家族と最後の夏を楽しみ、それが終わるときに、命を絶つというのが彼の計画であった。そして、自分がガンであることを、一人の友人を除いて、誰にも告げていなかった。自分の妻にまでも。
このシリーズのテーマは「嘘」、自分の妻に対しても嘘をついているわけである。その嘘を最後までつき通すことが出来て、彼は「計画」を完遂することが出来るのかというところが興味となる。
この主人公、哲学者である。
「彼は自分が幸せになる材料を必死で集めようとした。しかし、それで幸せが出来たかという自信はなかった。」
と書かれているが、彼のこれまでの生き方は、哲学者らしく「理詰めな」もの、幸せになれるであろう、「材料」を用意して、それによって幸せを「構築」していくものであった。しかし、ニューヨークでの体験からして、それが何時も上手く行かないことは、彼自身が知っている。
彼の性格を表すエピソードが面白い。彼は、生まれて初めての料理を試みる。パンケーキ、ホットケーキである。
「材料と、レシピがあれが、自分だって料理を作れないことはない。」
彼は言う。しかし、実際そうなのだろうかと私は思う。料理はレシピ通りに作っても、上手く作れるとは限らない。それを、自分で料理をする私は、一番良く知っている。
完璧であるはずの彼の計画に狂いが生じ始める。読者は、彼の計画が上手く行かないことをかなり早い段階で知る。そして、彼の計画は、読者も、彼自身も想像できない展開を迎える・・・
「リューゲンのヨハン・セバスティアン・バッハ」
Johan Sebastian Bach auf Rügen

彼は映画を見終わったが。それなりに心を打ち、将来への希望を暗示する結末だったが、涙は出なかった。映画のストーリーで、ひとりの女性が犯罪現場清掃業を営んでいた。彼女は金を失い苦境に立つが、父親が家を売って彼女を助ける。父親は彼女に、ワゴン車を買い与える。最後のシーン、娘が働く横で、父親も作業服姿で働いていた・・・彼はここ何年も泣いていなかった。最後に泣いたのは、父親と自分の政治的な立場について言い争ったときだった。いつも口論ばかりをしている父親だが、自分が本当に困ったとき、身体を張ってまで、助けてくれるだろうかと、彼は考える。
映画館を出た彼は、暖かい夏の夕方、歩いて帰ることにする。通りには人が出ている。彼はイタリア人の旅行者と出会う。親と子が仲良く歩いている。その光景を、彼は自分の父母とそんな関係になることは考えられなかった。彼は、親子の仲の良い旅行者に、少し嫉妬を感じる。彼は父親と、政治的な見解の違いで言い争った経験しか思い出せなかった。
家に帰った彼は、両親の家に電話をする。母親が出る。
「父さんと一緒に少し旅行がしたんだけど。」
彼は切り出す。父親の好きな海が見えて、バッハの音楽が聴けるところということで、彼はリューゲン島で催される、バッハ音楽祭に、父親と一緒に行くことを考えていた。
彼は父親をピックアップし、車でリューゲン島に向かう。音楽祭は、金曜日から日曜日までであった。父親は、裁判所の判事として働き、定年退職していた。車の中で、彼は父親と話すことがない。そのうちに父親は眠ってしまう。彼は、父親と一緒に休暇を過ごした経験がなかった。子供の頃、夏休みになると、彼と兄弟たちは、祖父母や親せきの家に送られていた。父親は、最初の妻と娘を作った後、妻を亡くしていた。彼は二番目の妻の子供だった。彼には、父親が、最初の妻との間に出来た姉を、亡くなった妻の分身のように可愛がっていたという記憶があった。
リューゲン島のホテルについたふたりは、翌朝一緒に朝食を取る。彼は、父親に、
「どうして、元々裁判官だったのに、一度弁護士になったんだ。」
と尋ねる。
「ナチスに反対した『告白教会』に助言して、ゲシュタポに睨まれてね。」
と父親は答える。朝食の後、ふたりは海岸へ散歩に出かける、父親はスーツにネクタイをして、革靴を履いている。
「一九四五年に、父さんの書いた論文を読んだけど、ナチスを擁護しているのはどうして?」
と彼は更に尋ねる。
「当時の様子は、お前には想像できないよ。生活を立て直す必要があって、それに懸命だったんだ。」
父親は答える。父親は戦後、裁判所の判事に復帰していた。
「どうして、私の論文を読む気になったんだ。」
父親は逆に尋ねる。
「友人が見ないかと送ってきたんだ。」
と彼は答える。
「『告白教会』を擁護したとき、不安はなかったの?」
彼の質問に対して、父親は答える。
「あったさ。その不安について、ずっと書きたいと思っていたけれど、まだ書くチャンスがない。」
最初のコンサートは夕方五時からだった。二人は三十分前に会場の教会に着いて最前列に座った。
「リューゲンでバッハ音楽祭が開かれるのは今年初めてなんだ。」
と彼は父親に言う。父親の反応は、
「何事にも最初があり、徐々に慣れていかなければならない。」
と父親答える。ピアニストが登場して、「イギリス組曲」と「フランス組曲」を演奏する。その演奏は、彼にとって、機械的な、冷たい弾き方に思えた。コンサートの後、ふたりはホテルに戻って食事を取る。
「今日の演奏は、余り心がこもっていなかったように思わない。観客が少なかったから、ピアニストの気が乗らなかったのかな。」
と彼は言う。
「いや、あれは一つの演奏法で、あんな風に解釈する奏者も多いんだ。」
父親はバッハの音楽について語りだす。彼は、父親が急に饒舌になったことに驚く。
「どうして、バッハの音楽を好きになったんだ?」
と彼は尋ねる。
「バッハは対立している物を融和させるんだ、まあ、ピアノを弾き始めた頃、バッハの曲しか弾かせてもらえなかったことも大きいが。」
と父親は言う。彼は、父親がピアノを弾くと聞いて驚く。
「どうしてピアノを止めたの?」
「定年になったらまた始めようと思ってたんだが・・・明日の朝も散歩しよう。おやすみ。」
父親は答えを濁して席を立つ。
翌朝彼と父親はまた散歩に出掛けた。岬まで歩いて、帰りはタクシーにした。歩いている間も、タクシーの中でも沈黙が続く。ふたりはコンサートに出掛ける。帰ってからの夕食の席でも、ふたりの間に会話はなかった。彼は、父親と自分の間にあるのは、「恒久講和」ではなく「一時停戦」だと思う。
「明日はもっと父さんと話そう。」
彼はそう決心する。
翌朝、彼と父親は、白亜の崖に沿って歩く。父親は、二度、リューゲン島に来たことがあるという。二度とも新婚旅行だったと父親は言う。その日のブログラムは、バッハのモテットだった。父親は、バッハのモテットの歌詞を全て知っていると言う。
「学生の頃、教会で歌ったんだ。」
と父親は行った。彼は、日曜日に、父親だけが教会に行っていたことを思い出した。三人の子供たちは教会に興味がなかったし、彼は父親と、宗教について話したこともなかった。二人は海岸に腰を掛ける。
「父さんは、若いころ、宗教的な大転換を経験したと母さんから聞いてるけど。それは、とても重要なことなんでしょ。どうして、僕や姉さんたちにそれを話さないの?姉さんはサンフランシスコにいるし、弟はジュネーブに行った。子供たちかどうして、父さんから離れたのか、それには理由があるんだ。何故、もっと子供たちに対して心を開かないの?」
彼は、父親に迫る。
「子供たちは、自分について十分に知っていると思ってた。」
そう言って、父親は立ち上がって歩き出す。
二人は最後のコンサートで、バッハのモテットを聴いた。彼は、バッハの宗教音楽はこれまで好きではなかったが、何故かその日は、音楽に感動し、陶酔した。コンサートが終わって夕食の後、ふたりは暗くなりかけた海岸を散歩した。彼は、父親との会話を諦めていた。
翌朝早く、二人は車でリューゲン島を去る。その車の中で、彼の考えていなかったことが起こる・・・
これまでのストーリーは男女の恋愛関係がテーマだったが、今回は、父親と息子の関係がテーマである。父親と息子の間の会話というのは一種独特であると思う。そこには、普通、母親と娘の会話のような饒舌はない。「途切れ途切れの会話」とでも言うのだろうか。私にももちろん父親がいたし、息子がいる。父親として、息子として、両方の立場でこの話を読んで、両方の立場を理解できて面白かった。
私事になるが、私の父も、自分の気持ちを上手に表現できる人ではなかった。仕事は別である。しかし、家庭では、それほど話をする人ではなかった。そして、自分も、そんな人間だと思う。私も、仕事においてや世間付き合いにおいては、普通に話をするが、家庭で、特に息子や娘に対して、話すのがそれほど得意ではない。そんな、父親と息子の、「途切れ途切れの」、「ぎこちない」会話が、このストーリーの中で、見事に表現されている。
この本の通例として、「彼」と「父親」として紹介されるだけで、固有名詞は一切出て来ない。「彼」の職業は明らかにされていないが、「父親」は法律家である。本当に、シュリンクは、自分と同じ立場の人を主人公に据えたがる。
「彼」は、映画と、イタリア人観光客から感化を受け、これまで疎遠だった父親との関係を修復しようと思い立つ。二人は、政治的な見解が異なり、「彼」の若い時は、顔を合わすと喧嘩ばかり。「彼」は、父親の好きな「海」と「バッハの音楽」を組み合わせて、リューゲン島で開催される「バッハ音楽祭」に八十二歳の父親を誘う。ふたりが、一緒に休暇を過ごすのは、何十年ぶりだと思われる。「彼」の、父親との「融和」の計画が、上手く行くかどうかというのが、この物語の焦点になる。寡黙な父親だが、バッハの音楽を語るときだけは、熱く、雄弁になる。それをきっかけに出来るのだろうか。
舞台になるリューゲン島であるが、バルト海にある、ドイツ最大の島であり、本土とは、橋でつながっている。ナチス政権時代、リューゲン島を一大保養地にする計画があったが、実現しないうちに大戦が始まり、ドイツが敗北した。写真で見る限り、風光明媚な島である。本当にこの島で「バッハ音楽祭」があったのか、調べてみたが分からなかった。
この書評を書きながら、私はバッハを聴いている。これまで「モテット」というのは余り聴いたことがなかったが、確かに素晴らしい。本と言うのは本当に良いと思える瞬間だ。これまで自分の知らなかった世界が広がる。どうしてバッハが好きなのかと聞かれたとき、父親が答える。
「バッハは対立している物を融和させる。」
その意味が良く分かる。さて、息子と父親はバッハによって融和されるのだろうか・・・
南への旅
Dir Reise nach
Süden

彼女は、子供たちを愛することを止めることにした。もう、子供たちとは没交渉でいたいと思った。理由は分からない。四人の子供たちはそれぞれ社会的に成功して、孫が十三人もいた。他人は、そんな子供たちを持った彼女のことを羨ましいという。また、これまで子供たちは、自分をしばしば訪れて、必要に応じて助けてくれた。彼女は自分の気持ちが一晩寝たら変わるかと思った。しかし、翌日も彼女の気持ちは変わらなかった。
彼女は、毎朝、森の中を散歩していた。誰にも言っていなかったが、彼女は、嗅覚と味覚を失っていた。夏の雨の後の森、そこはきっと良い匂いに包まれていると思われたが、彼女はそれを感じることができなかった、匂いを感じることのできない彼女は、特に、自分の匂いを気にしていた。嗅覚、味覚も、子供や孫たちと会うのに、必要なことだった。彼女の母、子供のある夫と結婚していた。
「どうして、前の奥さんの子供を愛することができたの。」
と彼女は母に尋ねたことがあった。
「努力したからよ。愛は意思の努力の結果なの。」
と母は言った。そうだとしたら、子供たちへの義務を果たした自分には、もう必要ないと思えた。しかし、子供たちへの愛を失ったことに対する空虚さは感じていた。彼女は、森の中のレストランまで来る。彼女は、そこまで夫と散歩をし、コーヒーを飲んだものだった。夫は秘書と不倫をしていた。それが発覚したとき、夫は、
「一番下の子供た学校を終えるまで、一緒にいてくれ。」
と彼女に懇願した。夫は、その秘書とは別れた。しかし、別の秘書とまた関係を持った。彼女は、夫と離婚した。
「他人のためではない、自分のための人生を送りたい。」
と彼女は思う。しかし、「自分のための人生」が何であるか、彼女自身が分からなかった。
彼女の誕生日。ドレスアップをして髪も整えた。四人の子供たちとその配偶者、十三人の孫たちがやって来た。皆は、昼食を取りに、森の中のレストランへ向かう。
食事が始まる。彼女は、スターリンが、写真に一緒に写っていたトロツキストたちを、最初からいないように、写真から抹殺したことを思い出していた。
「父親の話をしたら、私が気分を害するとでも思っているの?この前、父親の八十歳の誕生日を、彼の妻とお祝いしたんでしょ。」
彼女は息子に言う。
「いや、母さんが、父さんのことを一切話題にしないから・・・」
と息子が困惑して話し出す。
「私が怒り狂い、あんたたちと父親が会うのを禁止するとでも思ったの?」
「母さん、ウェートレスが待ってるじゃないか。」
「ウェートレスの予定がそんなに大事なの?」
と彼女は息子に詰め寄る。彼女は、周囲になだめられる。
食事が終わって、一番年少の孫がスピーチを始める。
「お祖母ちゃん。僕たちに、本を読む楽しさを教えてくれてありがとう。お祖父ちゃんやアニにもそうして欲しかった。」
彼女は、顔色を変える。
「『アニ』って誰なの?」
と彼女は娘に尋ねる。
「お父さんの二人目の奥さんよ。『お祖母ちゃん』でなく『アニ』って呼んで欲しいって言っているの。」
「お母さん、もう止めて。」
「止めてって、私が始めたんじゃないわ。」
彼女は、
「疲れたから少し休みたい。二時間したら迎えに来て。」
そう言って、レストランを去る。彼女は、二時間後に、一番年上の孫にピックアップされるが、もう、誰とも話したくない気分だった。
その後、彼女は病を得る。子供たちのアレンジで、孫娘のエミリアが看病に来る。熱にうなされた彼女は、若いころの夢を見ていた。彼女は、片腕の男と踊っていた・・・
「ラ・ラ・ランド」という映画がある。二〇一六年に、数々の賞を受けたミュージカルである。私の好きな映画だ。特に、最後のシーン、主人公の女優、彼女はかつての恋人と別れ、女優としての人生を歩み、成功し、別の男性と結婚し、幸せな生活を送っている。しかし、
「かつての恋人と一緒になっていたら、自分は・・・」
と考える。そして、その生活を走馬灯のように夢見る。しかし、夢は終わり、彼女は現実に戻る。人間、二つの人生を経験することはできない。しかし、
「もし、自分があのとき別の選択をしていたら、自分は今、どのような生活を送っているだろうか。」
と考える。自分もずっとそう思っていたことに気付き、泣けた。
この「南への旅」のテーマも、まさにそこにある。老年を迎えた女性、ずっと「彼女」としか書かれていないが、最後の方でニーナという名前だと分かる。彼女は、不倫をした夫と離婚し、四人の子供を育て上げた。そして、自分の人生が終わりに近づいていることを感じる。彼女は、
「子供も、孫も愛することはやめよう。自分だけを愛して、残りの人生を自分のためだけに生きよう。」
と決心する。
彼女は病を得る。看病をしてくれたのは、孫娘の一人で、大学で医学を目指すエミリアに看病される。ようやく回復した彼女は、エミリアに、
「南へ向かって旅をしよう。」
と提案する。エミリアの運転で、二人は「南」へ向かう。そこは、ニーナがかつて大学に通った町であった。彼女は、一九四〇年代の終わり、その町で、片腕の学生アダルベルト・パウルセンと出会った。しかし、ふたりは突然の別れを迎える。ニーナは、エミリアにその話をする。朝食のとき、エミリアがいない。戻ってきたエミリアは、アダルベルト・パウルセンを探し出し、祖母と会う手はずを整えていた。
ニーナは、人生で、アダルベルトと別れたことをずっと後悔していた。そして、心の底で
「もし彼と一緒になっていたら。」
と考えていた。老年を迎え、やり直しの効かない年齢になり、彼女は、その答えを知る。そして、その答えは・・・余りにも切ない。アダルベルトの言葉が全てを語っている。
「どの人生が正しくて、どの人生が誤りだということはないと思う。単に違う人生というだけだ。」
人生における選択が正しいものであったがどうかを決めるのは、その人が、その選択を正しいものにするという、その後の努力次第なのである。
この物語、六十歳を過ぎた今の自分と重ね合わせて読むと、特に心に沁みる。今回も「嘘」がテーマになる。しかし、誰が誰につき続けてた嘘なのか、それは書かないでおくことにする。 この短編集、どの物語も良かったが、特に最後の二編は心に残った。それは、やはり、登場人物の年齢に近く、自分を彼らに重ね合わせることができたからだと思う。
(2020年9月)